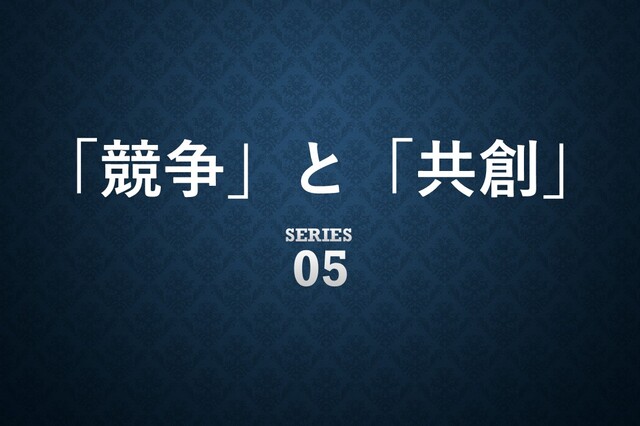/ユダヤ人(セファルディム、ローマン、アシュケナジム)やシーア・イスラム諸派、クルド人、グノーシス・カタリ教徒、ドルーズ(ムワヒドゥン)教徒、現代でも紛争の種となるこれらの人々は、中世の東西文明の軋轢から生まれた。/
「ついにノルマン人は国を手に入れた」
神聖ローマ皇帝ハインリヒ四世(c1050-th84-1106)は、ライン河のユダヤ人たちを利用して、サクソン人を搾取し、別の教皇を任命することで教会に介入しました。サクソン人の領主たちが反乱を起こすと、ノルマン人と繋がるグレゴリウス七世(c1015-th73-85)もハインリヒ四世を破門し、廃位しました。そのため、ハインリヒ四世は1077年にカノッサへ赴き、グレゴリウス七世に謝罪しなければなりませんでした。しかし、ハインリヒ四世は1081年にローマを攻撃し、グレゴリウス七世を追放し、代わりに傀儡の教皇を即位させました。
「教皇、皇帝、ノルマン人、そしてユダヤ人、これらは厄介なオールスターだった」
テュルク系セルジューク帝国は、北東ペルシア出身の数学と天文学の天才、オマル・ハイヤーム(1048-1131)を首都バグダードに招聘しました。彼はヨーロッパ暦よりも正確なジャラリ暦を創りました。彼は詩人としても才能があり、ワインと美しい女性を称え、無常を詠ったルバイヤート(四行詩)を数多く書きましたが、宗教的非難を避けるため出版はしませんでした。
「セルジューク族はテュルク系だったけど、ペルシア人を尊重したんだ」
ペルシア人のアル・ガザーリー(c1058-1111)、別名アルガゼルスは、地元のニザーミエ学院に学び、首都バグダードのニザーミエ大学の教授に任命されました。彼は正統的な法学と神学を基盤としながらも、ウラマー(知識人)の空虚な権威とイマームへの盲目的な依存に危機感を抱き、同時にスーフィズムも学んで、神の非物質的な形而上学を探求しました。
「彼は自由で、開かれた学者だった」
ノルマン時代のイングランドでは、アンセルムス(1033-1109)も、実在論を通して神の形而上学の探求を試みていました。彼は、神は最も偉大な存在であり、人間の思考を超えるものは、現実に存在するはずだ、と主張しました。一方、パリの修道士ロスケリヌス(c1050-c1121)は、「神」は単なる言葉の名称に過ぎないと論じました。なぜなら、「神」が実体であるならば、創造主と聖霊もまたイエスと共に受肉したに違いないからです。
「どちらの議論も、こじつけだな」
ロスケリヌスは、三神論者の疑いをかけられ、1092年にイングランドへ逃げ、そこで、彼はアンセルムスと普遍問題を論争しましたが、敗北して追放されました。そこでロスケリヌスはローマへ赴き、名前の不存在と独立性を説き、誤解を解こうとした。イングランドのノルマン王からカンタベリー大司教の任命に多額の資金を要求され、アンセルムスも、ローマへ逃げざるをえませんでした。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る