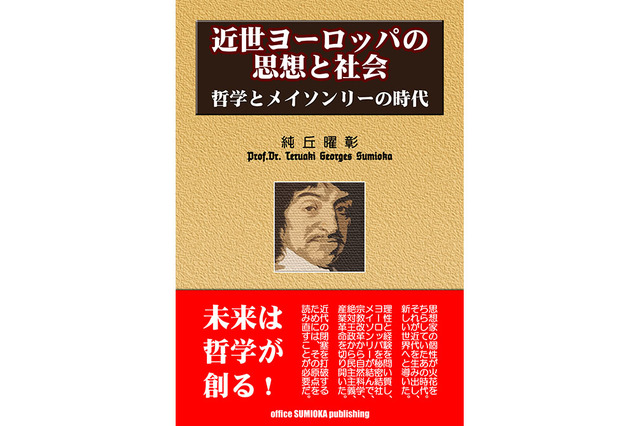/産業革命は、たんなる生産経済の効率化でなく、社会構造を根底から変えた。/
そして、その後も、犯罪者が被害者を殺して口を封じるように、政府は、土地を求める移住者の声に従って、何億ドルもの資金を投じて繰り返しインディアンの土地を侵略しました。そして、その侵略は、ジェロニモ率いるアパッチ族を八六年に降伏させるまで続き、その後もなお、第一次大戦の始まる一九一四年まで、彼らを囚人として留置したのです。しかし、移民の増え続けるアメリカは、西部の広大な土地の必要性を、その罪悪感ゆえの脅迫妄想で自己完結的に最後まで正当化してしました。これは、後に見るように、運命説と陰謀説とからなる大衆的発想の典型的な一例と言うことができるでしょう。
8 平等で険悪な社会
さて、産業社会において、工場では、次第に水力や蒸気による機械化が進み、また、流れ作業として分業化されていることもあって、そこでの作業は、婦人や子供でもできる体力も技能もいらない単純反復労働になっていきます。そして、ここでは、誰もがみな、性別も年齢も関係なく均質で代替可能な「労働者」となるのです。
では、その雇用者の方は、個性豊かな生活を送ったか、というと、そうでもありません。彼らにしても、とりあえず作っている商品と言えば、繊維とか、鉄鋼とか、鉄道とか、きわめて種類が限られていました。そして、技術の進歩は、今日に比べればきわめて緩やかでしたから、他人との差別化など図りようもありません。ましてや、ようやく登場しつつあった金融資本家の扱う商品ときたら、それは貨幣であり、誰が持ってもまったく同じ価値と意味を持つものにきまっていました。
ヨーロッパ産業社会のような悲惨さはないとはいえ、アメリカにおいても、事情は似たようなものでした。つまり、誰もがただ畑を耕す「農民」になったのです。ここでは土地は有り余っており、誰も小作になる必要はありませんでした。たしかに、新興の産業家や大地主も生れましたが、ヨーロッパのようにぞんざいに使用人を扱えば、奴隷でもない限り、次の日には、みな自分の農園を作りに出て行ってしまったでしょう。
しかし、ヨーロッパにおいても、アメリカにおいても、このようにして成立した近代人たちは、たとえまったく同じ仕事をしていても、まださまざまな経歴を引きずった寄せ集めであり、工場や産業やタウンごとに新たな共同体を築くのには、まだしばらく時間がかかります。いや、それどころか、生産過剰に、同じ工場や産業やタウンの中でも、出身地や元の身分、宗教などによる激しい対立があったのです。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る