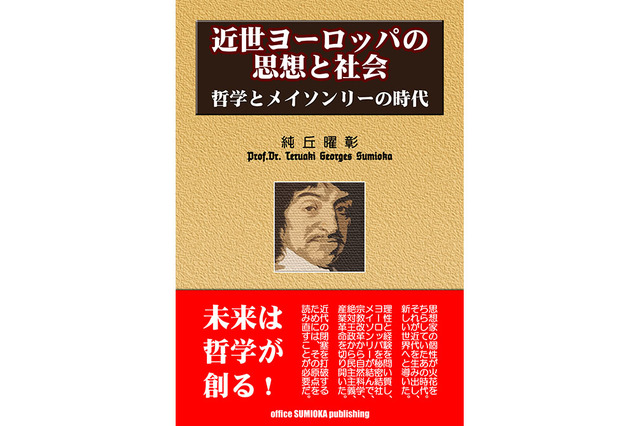/産業革命は、たんなる生産経済の効率化でなく、社会構造を根底から変えた。/
一方、工場主、商店主、家主などの中には、この産業革命周辺の製造・販売・賃貸等に関与することで、小銭を貯める人々も出てきます。これに応じて、ナポレオン戦争の前後に、イギリス、次いで、アメリカで貯蓄銀行が、また、フランスでは供託局がいくつかできます。一七九九年、イギリスのバッキンガムにできた最初の貯蓄銀行は、「最大多数の最大幸福」を唱えた弁護士にして哲学者のジェレミー=ベンサムの助言に基づくものでした。もちろん、銀行は、アムステルダムでは一六〇九年に開行し、イギリスでも、イングランド銀行が一六九四年にはできていますが、これらは基本的に通貨の交換ないし保証のためのものです。人々の小銭を預金として受け付け、代わって投資して利子を付ける銀行は、ようやくこのころ普及していったのです。
父親の仕事の失敗で小学校も卒業しないままに靴墨工場で働かなければならなかったこともあるチャールズ=ディケンズは、やがてロンドンの新聞通信員となり、一八三六年、二四歳で小説を書き始めます。さらに、彼は、『オリバー=ツイスト』を雑誌に連載し、読者の支持を得、社会派の小説家としてのゆるぎない地位を獲得します。その小説の主人公オリバーは、ロンドンの貧民窟の純心な孤児であり、その翻弄される運命とともに、犯罪者ビルや娼婦ナンシー、盗品流しのフェイギンなどを通じて、貧民窟に暮す人々の姿をせきららに描写し、政府の救貧法の欺瞞を暴きました。
さらにまた、四三年、彼は『クリスマスキャロル』で、小市民の商売人スクルージを描き出します。クリスマスに食べるものも着るものもない人々ための寄付を求める紳士に、このスクルージは「監獄があるじゃないか」と答え、「怠け者のための金のゆとりなんて、わしにはないんだ。施設の維持費は、わしだって出してるんですぞ。」と開き直り、「施設に行くくらいなら死んだ方がましだなどと言うなら、死んであり余る人口を減らしてくれても結構だね。」と言って追い返します。それでも、紳士が「でも、あなたは問題がおわかりでしょう。」と言葉をはさむと、スクルージは「それは、わしには関係ないこと。自分のやっていることがわかっていたら、他人のことなんか口出ししている暇はないんだ。」と得意げに言い返すのです。小説に誇張されているとはいえ、これが、小金を持つ小市民たちの誰もの心にひそむ本音の一端だったことでしょう。多少の金もまた、この時代には心の貧しさを深めるだけでした。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る