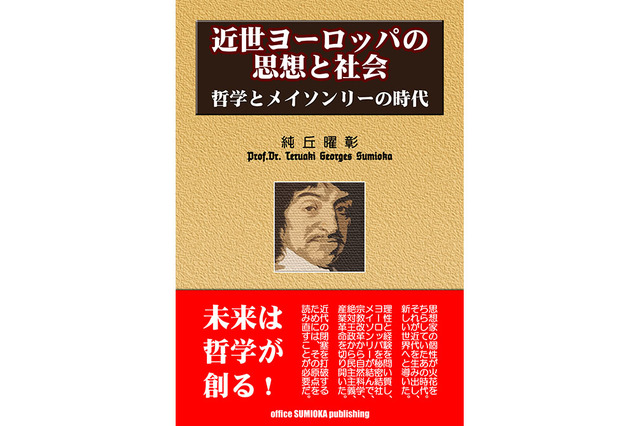/産業革命は、たんなる生産経済の効率化でなく、社会構造を根底から変えた。/
このように、十九世紀初頭に、鉄の量産をきっかけとして、湖川・運河では蒸気船が、外洋では高速大型帆船が、内陸では汽車鉄道が活躍し、世界中に交通網が建設されるようになっていったのです。ただし、産業の中心は、あくまで綿製品などの半農半工的なものであり、いわゆる工業社会とはほど遠いものでした。
6 最初の世界不況
このような鉄によるめざましい国土の変貌の一方、社会も大きく変質を遂げつつありました。というのも、ナポレオン戦争によって、産業革命の様相は一変してしまったからです。戦争も終わって、軍隊の大量の需要もなくなった今、各国ともに、完全に物資の生産過剰となってしまったのです。加えて、何十万人もの除隊者が、失業者として帰国してきました。そして、なにより、気候のせいか、戦争のせいか、この時期、ヨーロッパの人口そのものが爆発的に急増してしまいます。アメリカはただちに二五パーセントもの関税をかけて、自国の産業の保護に乗り出しました。それでも、次第に不況は深刻化していき、三七年、綿花輸出業者の倒産をきっかけに、金融恐慌となって数万人もの破産者を出し、さらにその不況は、ヨーロッパにも広がっていったのです。
産業革命は、イギリス一国で進行し、そこだけが世界の工場であったうちは、まだ幸せでした。ナポレオン戦争後、アメリカもフランスも、そして、後にはドイツもロシアも、同じように世界の工場たるほどの生産力を獲得してしまいました。この生産過剰は、イギリスやフランスでは弱小な農家や手工業者を没落させ、都市の賃金労働者に変えていきました。それも、戦後の労働力の供給過剰によって、むしろ劣悪な労働条件に落ちていったのです。そして、このことは、国民一般の購買力を低下させ、さらに多くの弱小な農家や手工業者を没落させていきます。
彼らは、もはや田舎では生活できませんでした。そこには、もはや土地も職もないからです。そこで、全財産を処分して旅費を都合し、徒歩で、また、ようやく整備された鉄道などを使ってとりあえず都市へ出てきます。しかし、都市でも状況は似たようなものでした。しかし、もはや彼らは帰ることもできないし、帰る所もないのです。こうして、曲がりくねった狭い路地、悪臭と汚水、窓ガラスもなく傷んだアパート、このようなセントジャイルズの「貧民窟」が、まさに繁栄を誇るイギリスの首都ロンドンの真ん中に出現したのでした。
イギリスでは、すでに一六〇一年に「救貧法」、すなわち、貧者を救済する「慈悲深い」法律が制定されていました。それは、つまり、教区内に住む貧者はその教区が扶養する、というものでした。しかし、それは近代以前の、社会の固定した近世にこそふさわしい法律でした。近代になってこのように多くの貧者が都市に流入してくるようになって何が起こったかと言えば、都市の人々は、とにかくこのような扶養義務を生じるような流入貧者を少なくとも自分の教区には住まわせないように奔走したのです。つまり、流入してきた貧者を買収し、ひそかに他の教区へと追放し、その扶養義務を免れようとしたのです。もちろん、たしかに都市では地方よりは労働力を必要としていましたが、しかし、教区に定住させないために、一年奉公という古くからの慣習の方が放棄されてしまいました。つまり、せいぜい短期にしか雇用しなくなってしまったのです。このようにして、貧者の誰ひとりこの救貧法で救済されることなく、それどころか、この法律のためにかえって安定した定住も就職もできず、結局は「貧民窟」に暮し、日々仕事を求め歩くしかありませんでした。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る