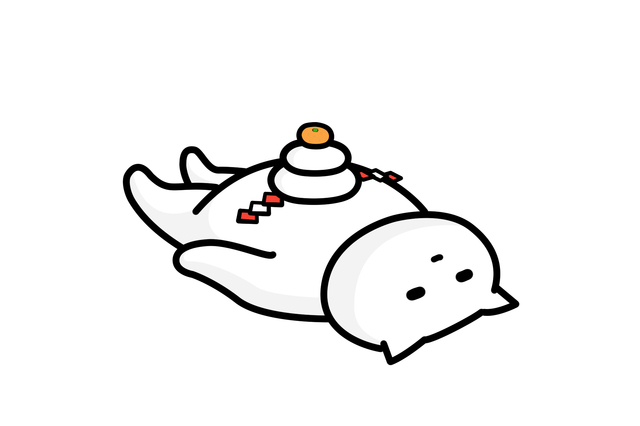「『9月入学』を目的化すべきでない」という論者もいる。しかし、日本の学生の海外留学と外国人留学生の受け入れをしやすくし、ひいては日本の若者と教育現場に多様性の価値観をもたらすという大義は正しく、それが大目的になると考えるので、小生は大賛成だ。問題はその方法論。ここに私案を提示したい。
コロナ騒ぎにより全国で休校が続いた中、「これを機会に世界で主流の『9月入学』を真剣に検討して欲しい」という現役高校生からの提案をきっかけに『9月入学』論争が急浮上してきた。
当初からあまり積極的ではない文科省は、それでも政府・与党からの要請を受け『9月入学制』への移行に関し2案を先に示し、最近追加で「ゼロ年生」導入案というのを持ち出してきた。しかしいずれも課題ばかりが大きく、「やっぱり無理なのか」と世論を断念させる思惑が強そうだ。
そこで以下に、「意外と課題が小さい方法があるじゃないか」と思える私案を提示したい。
1.9月入学への移行案
ポイントは1つ。特定の「調整学年」を設け、小学校入学から大学卒業までずっと「5ケ月間の生まれ」の小規模学年として移行させるのだ。図を参照されたい。

来年の小学1年生は通常なら2014年4月~2015年3月生まれ(注)の12ケ月間に生まれた子供たちが対象だ。それを、2014年4~8月生まれの5ケ月間に生まれた子供たちだけに、旧制度最後の学年として5/8サイズの「調整学年」となって入学してもらうのだ。
注:正確には今の各学年は4月2日生まれから翌年の4月1日生まれで構成されている。本図では簡略化のためにそれを4月から翌年3月と表現している。
彼らが4月に入学した5ケ月後の9月に、再び入学式を行う。対象は2014年9月~2015年8月の12ケ月間に生まれた「新制度学年」の子供たちだ(図参照)。つまりこの時点で各小学校には7つの学年が存在することになる。そして6年後の3月に「調整学年」が卒業した時点以降、学年数は6つに戻り生徒数も通常に戻る。
その同じ年の4月、今度は中学校で調整が始まる。5/8サイズの「調整学年」が4月に入学し、その5ケ月後の9月に再び入学式を行い、次の「新制度学年」の生徒たちを迎えることで各中学校には4つの学年が存在する。そして3年後の3月に「調整学年」が卒業した時点以降、学年数は3つに戻り生徒数も通常に戻る。
この調整の波は、「調整学年」の入学・卒業と共に順次、高校そして大学へと移行していく。各小学校・中学校・高校・大学とも2回ずつ、入学式を2回と卒業式を2回行う年度が巡ってくるということだ。
さて、「調整学年」を含む旧・4月入学制の生徒たちと新・9月入学制の生徒たちが混在する期間、各学校の始業式と終業式には混乱はないのだろうか。これについては9月入学制の学年終業のタイミングだけ工夫すれば(欧米は5~6月にしているケースが多いが、日本では7月にすればよい)、特に心配は要らないのではないか。
社会インフラ・制度
2019.07.25
2020.03.11
2020.04.08
2020.05.10
2020.05.25
2020.11.18
2020.12.16
2021.01.06
2021.01.20
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け38年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る