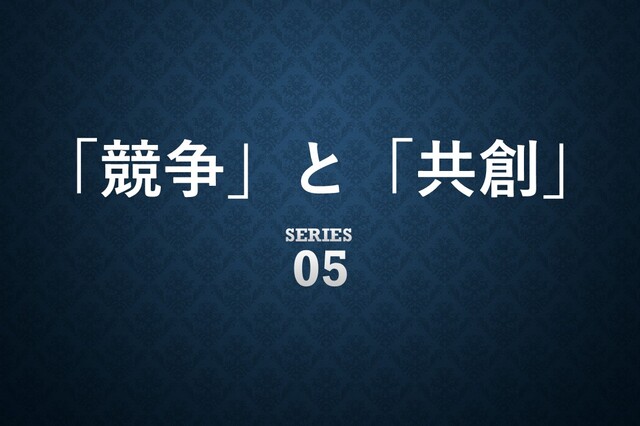NPO法人「老いの工学研究所」で高齢社会に関する研究活動を続けながら、企業にシニアマーケットに関するコンサルティング、研修・セミナーなどを提供されている川口さん。これから超高齢化社会を迎える日本にとって、必要な視点についてお話をうかがいました。(聞き手:猪口真)
猪口 メディアが報道するような高齢者についての情報、あるいは、シニア世代に対する一般的な既成概念もあります。そういったものと、川口さんが企業に行ってコンサルティングをされるときにご提案される視点には、どのような違いがありますか。
川口 違いは明確です。メディアは一般的に、生活費の不足、孤独、病気、そういったことを二つも三つも持っているような、いわゆるかわいそうな老人として、描くことが多いと思います。たしかに、そういう人を何とかしてあげるのは大事なことです。しかし、そういう人は現実として少数派です。毎年発表される高齢者白書の「経済的に暮らし向きはどうですか」という質問では、「全く心配ない」「あまり心配がない」「やや心配だ」という人を合わせると、約95%になります。ですから、お金は持っているのです。さらに、先ほど申し上げたように、10歳くらい若返って健康です。85歳を超えても、要介護2以上の人は23%しかいません。80代前半まではほとんど要介護状態ではないので、元気な人にいかに最期を楽しく過ごしてもらうかが大事です。
ところが、企業の多くがそうした報道を見て、かわいそうな人を助けようという考えになってしまっています。それは国がやることであって、企業でできることではありません。元気な人を楽しませるのが民間企業のやることで、かわいそうな1割を助けるのは国の仕事です。多くの企業の人たちが思い込んでしまっているので、そこを切り替えてもらうのに、かなりの時間がかかります。「ケア」という思考になってしまうのが、企業がシニア向けの新しいビジネスをなかなか作れない理由だと思います。

猪口 最近ではサービス付きのマンションも好調です。サービスは欲しいけど「サ高住」は嫌という元気な方が多くいらっしゃるようです。5年、10年のスパンで見ると、シニアの方々はさらに変わっていくのでしょうか。
川口 変わると思います。健康状態はさらに良くなるでしょう。僕が注目しているのは、団塊の世代が75歳に差し掛かっていることです。団塊の世代の価値観は少し違うと言われていますから、高齢者ゾーンがどのような生活スタイルになるのか注目しています。また、これは団塊の世代に限りませんが、子どもにお金を残す人が減っていくと思います。自分のために使う人が増えてくるのではないでしょうか。今の80歳後半から90歳くらいの人は、質素、倹約が身に付いています。戦後すぐの食べ物がなかったような時代を経験している人たちは、お金を持っていても、贅沢は敵なので使いません。贅沢するのは恥ずかしいと言う方もいます。
次のページ企業もソフトランディングのためにサポートすべき
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
インサイトナウ編集長対談
2022.03.16
2022.08.12