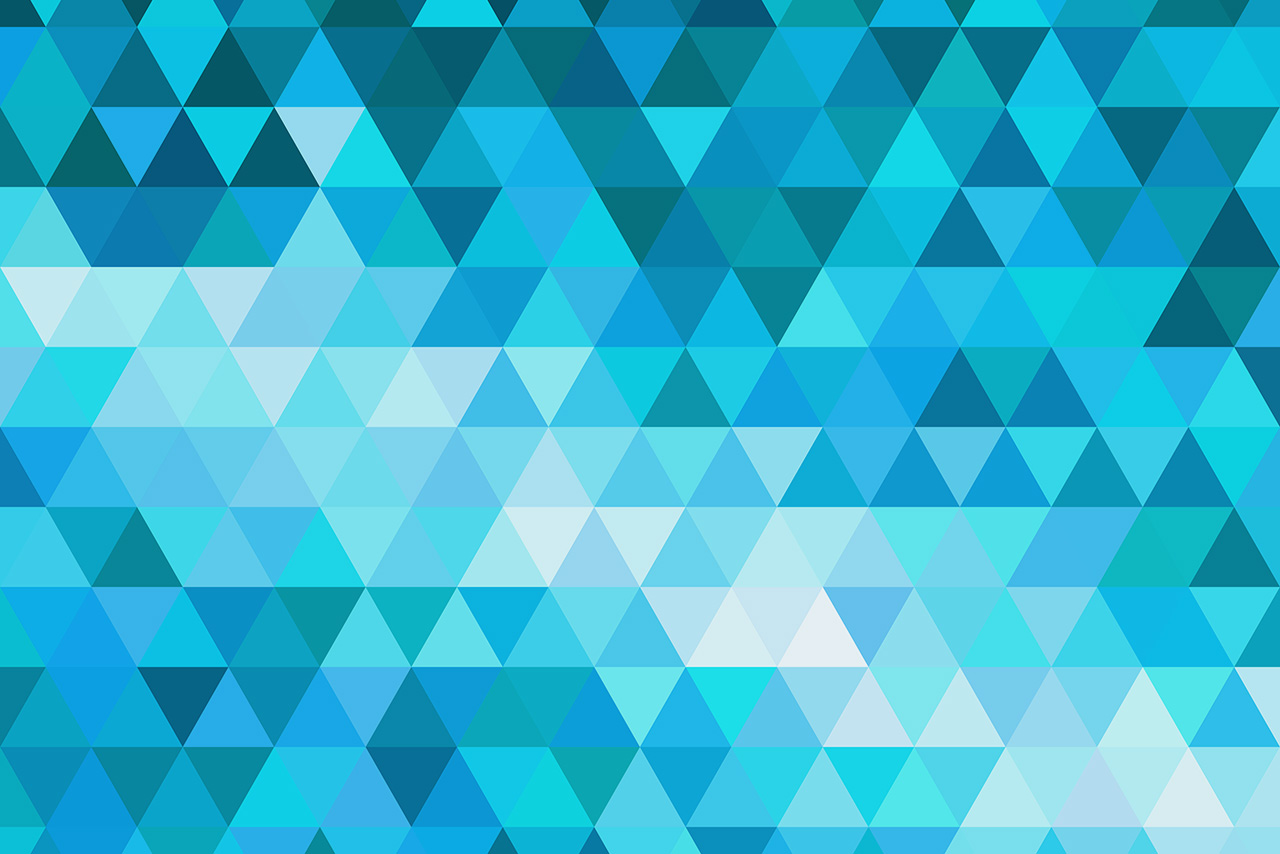2025.08.04
「もう指示されたくないんです」──若手のつぶやきが意味するもの
齋藤 秀樹
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
“問いかけ”が人を育てる ― 上司が“答えを教える時代”は終わった ― 「もう指示されたくないんです」──若手のつぶやきが意味するもの 「うちの若手、指示しないと動かないんですよ」 ある管理職がこうぼやいた。だが、同じ若手の口からは、まったく逆の言葉が聞こえてくる。 「上司って、なんで“指示”しかしないんでしょう。もっと、自分で考えたいんですけど」 このズレこそが、今の組織で起きている本質的な問題だ。 上司は「自分の経験」を伝えようとする。部下は「自分のやり方」を試したい。前提も価値観も異なるまま、コミュニケーションの回路はすれ違い続けている。
組織の未来は、この連鎖をどれだけ生み出せるかにかかっている。
■ 「問い」をマネジメントの中心に据える
「育成とは、“答え”ではなく“問い”を残すことだ。」
この言葉を、あるリーダーは大切にしている。
会議でも1on1でも、最初に“問い”を準備する。上司が話す時間を意識的に減らす。
話すよりも「引き出す」。決めるよりも「考えさせる」。
それだけで、チームは少しずつ変わっていく。
問いをマネジメントの中心に据えることは、リーダー自身の在り方をも問い直すことになる。
──あなたは、正解を与えるリーダーですか?
──それとも、問いかけによって育てるリーダーですか?
その選択が、これからの組織の姿を決めていく。
■ 自立と創造性を引き出す「問いの技術」
「部下が自分から考え、行動するようになってほしい」
そう願うなら、上司の“問い”の質が試される。
問いには段階がある。最初は「事実確認」、次に「意図確認」、そして「未来への創造」だ。
たとえばこんな流れだ:
- 何をした?(行動確認)
- 何が起きた?(事実観察)
- なぜ、そのような結果になった?(結果洞察)
- 次はどうしたい?(未来への創造)
この4ステップの問いを日常に織り込むことで、部下の中に「考える習慣」が生まれていく。注意点はこのプロセスに自分の判断を持ち込まないこと。判断を持ち込むと自分の答えに誘導することになる。これはやらされ感の源泉だ。
そして特に、最後の「未来への問い」は重要だ。
過去を振り返らせる問いばかりでは、部下は反省モードに陥る。
「次はどうしたい?」「そのとき、何ができそう?」と未来に視点を向けさせることで、前向きな思考が育つ。
創造性とは、「過去の答え」ではなく「未来の問い」から生まれるものだ。
■ 成果を生むリーダーは、問いを“手放さない”
「正解を出すリーダー」と、「問い続けるリーダー」。
どちらが、チームを成長させるか。
答えは明らかだ。
成果を出すリーダーは、決して「問い」を手放さない。
むしろ、自らに問い、チームに問い、組織に問い続ける。
なぜなら、現代は「変化のスピード」が速く、過去の成功パターンが通用しなくなる時代だからだ。
今日の“正解”が、明日には“間違い”になるかもしれない。
だからこそ、問いを持ち続ける姿勢こそが、変化に強いチームを育てる源泉になる。
問いとは、思考のエンジンであり、創造の火種である。
リーダーが問いを手放さない限り、チームも前進をやめない。
■ 「問い」でつくる心理的安全と信頼
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る