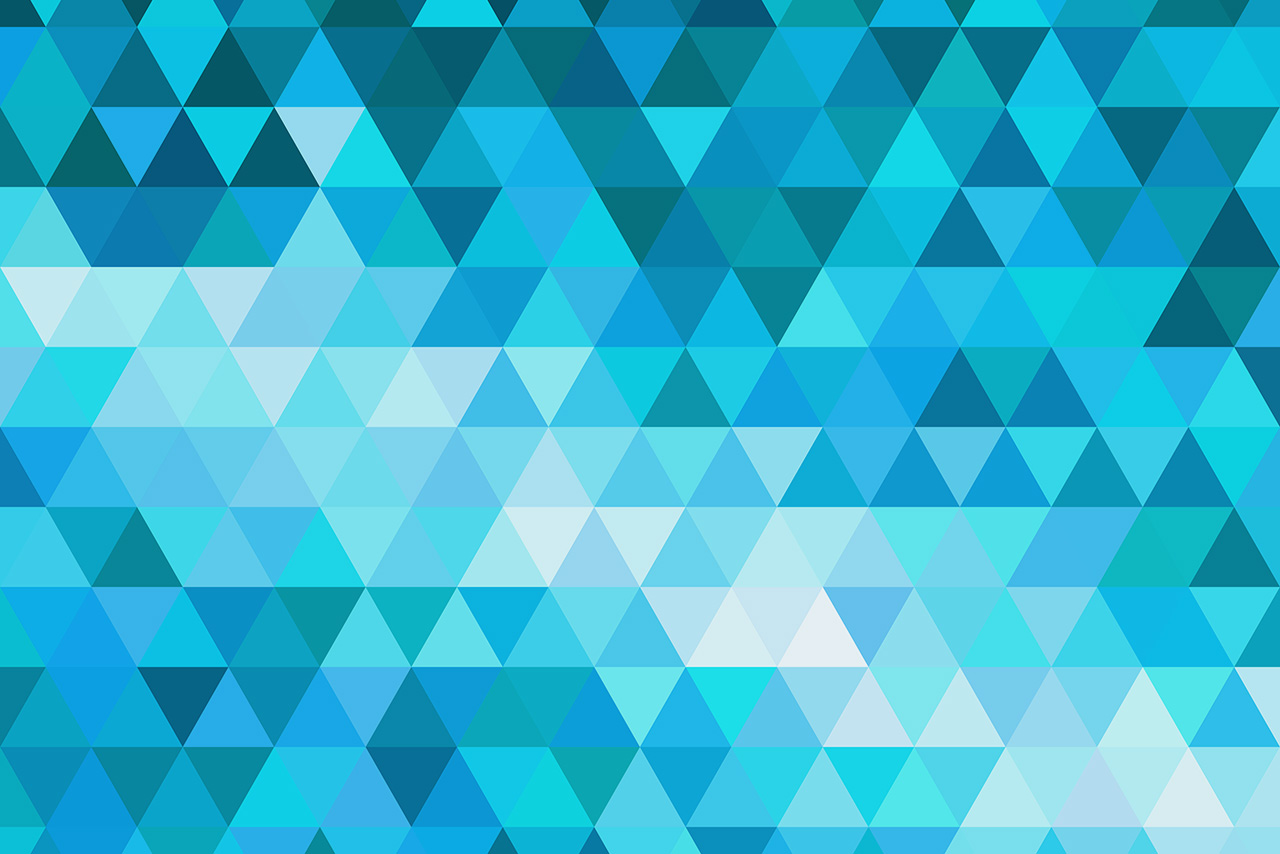2025.08.04
「もう指示されたくないんです」──若手のつぶやきが意味するもの
齋藤 秀樹
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
“問いかけ”が人を育てる ― 上司が“答えを教える時代”は終わった ― 「もう指示されたくないんです」──若手のつぶやきが意味するもの 「うちの若手、指示しないと動かないんですよ」 ある管理職がこうぼやいた。だが、同じ若手の口からは、まったく逆の言葉が聞こえてくる。 「上司って、なんで“指示”しかしないんでしょう。もっと、自分で考えたいんですけど」 このズレこそが、今の組織で起きている本質的な問題だ。 上司は「自分の経験」を伝えようとする。部下は「自分のやり方」を試したい。前提も価値観も異なるまま、コミュニケーションの回路はすれ違い続けている。
“問いかけ”が人を育てる
― 上司が“答えを教える時代”は終わった ―
■ 「もう指示されたくないんです」──若手のつぶやきが意味するもの
「うちの若手、指示しないと動かないんですよ」
ある管理職がこうぼやいた。だが、同じ若手の口からは、まったく逆の言葉が聞こえてくる。
「上司って、なんで“指示”しかしないんでしょう。もっと、自分で考えたいんですけど」
このズレこそが、今の組織で起きている本質的な問題だ。
上司は「自分の経験」を伝えようとする。部下は「自分のやり方」を試したい。前提も価値観も異なるまま、コミュニケーションの回路はすれ違い続けている。
特にZ世代に代表される若手社員たちは、「納得感」や「自己決定感」を強く求める。だからこそ、上司の一方的な“答え”には、拒否反応すら示す。
いま、現場で本当に必要とされているのは、「問いかけ」によって部下の思考を引き出す、コーチング型のマネジメントである。
■ 上司の“問い”が、部下の「思考回路」をつくる
「なぜ、そう思ったの?」
「次にどうしたい?」
「それを実現するために、何が必要だと思う?」
──これは、ある企業のリーダーが日々部下に投げかけている“問い”だ。
決して難しい質問ではない。だが、この問いの積み重ねが、部下の思考回路を耕し、自立性を育んでいく。
問いかけることで、部下は初めて「自分の中にある答え」に気づいていく。上司が先回りして答えを与えてしまえば、その芽はつぶれてしまう。
特に若手社員は、「正解を外注する」ことに慣れすぎている。学生時代から与えられた問いに“正解”で応える訓練はしてきたが、「問いを立てる訓練」はされていない。
だからこそ、上司が「正解を教える」のではなく、「問いを投げかける」存在であることが、彼らの成長には決定的に重要なのだ。
■ 教える時代の終焉と、「育てるリーダー」への進化
旧来のマネジメントは、「上司=知っている人」「部下=知らない人」という構造に依存していた。
だが、情報が飽和し、AIさえ活用できる今、「知っていること」自体の価値は相対的に下がっている。
部下が求めているのは、「正解」ではなく、「一緒に考えてくれる存在」だ。時には失敗しても、そのプロセスを共に見守り、支え、内省へと導いてくれる人。
これこそが、「育てるリーダー」である。
育てるリーダーは、「手本になる」のではない。「探求の伴走者」となる。
問いを通じて、自分の頭で考え、答えを見つけ、時には迷いながらでも進んでいく。そうして育った部下は、やがて「誰かを育てる人」へと進化していく。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る