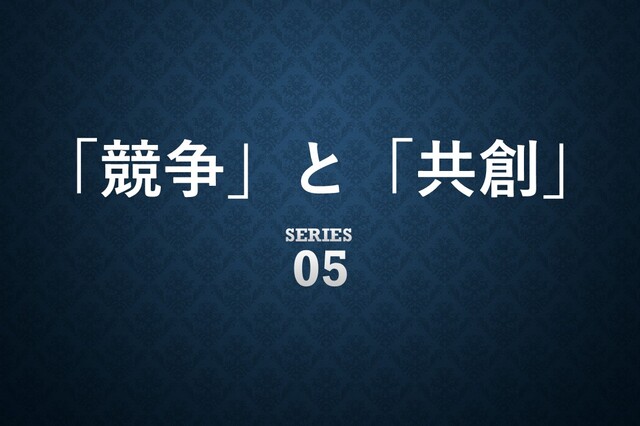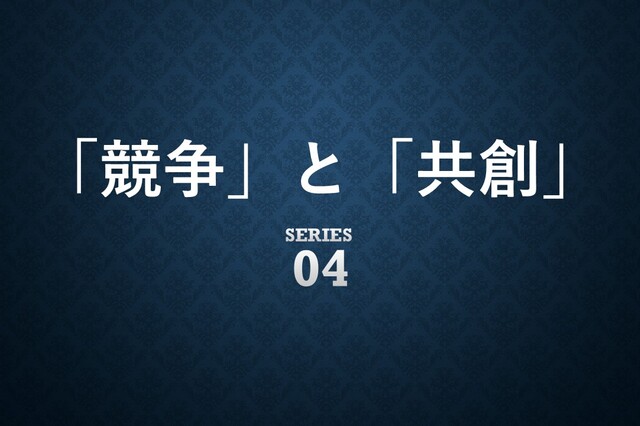生成AIの活用事例が想像以上に大きくなっている中、マーケティングや人材開発といった、ビジネスの現場においてはどのような広がりを見せているのか。 すでに生成AIを使ってビジネスアウトプットを出されている金森さん、富士さんに現場レベルでの生成AIの活用状況をお聞きしました。
お相手:マーケティングコンサルタント金森努様×人材開発コンサルタント富士翔大郎様
生成AIはもはや日常の一部
猪口:今日はマーケティングにおける生成AIの応用事例について話をうかがいます。まず、現在のAIの普及状況についてご意見をお聞かせください。
富士:2024年時点で、アメリカではインターネット利用者の約35%、日本では約20%が生成AIを日常的に利用しているといわれています。2年前と比較すると普及率は2倍以上と、爆発的な広がりを見せています。10年前には「AIに奪われる職業」として予測されていたものが、現在では大きく変わっています。特に、当初は生き残ると予測されていたクリエイティブな職種が影響を受けており、コピーライターやシナリオライター、グラフィックデザイナーなどはAIに大きな影響を受けていると言われています。一方で、介護士や保育士のような体を使う職種は当初の予測とは逆に、まだAIに代替されにくい職種となっています。
金森:私自身も趣味で生成AIを活用して小説を書いているんです。プロットや登場人物の設定などの素地を考えて、「こんな感じで書いて、1章ごとにチェックして進めていきましょう」と文体や表現上の留意点などを詳細に指示すれば、AIが文章を生成し、それを加筆修正しながら進めることができます。
富士:画像、映像、音楽、文章など人間が作っていたアート作品のほとんどはAIが作れるようになって、AIが90%以上書いた小説が文芸賞に入選するレベルになっています。しかし、実際にビジネスシーンでAIを活用している人は少数派で、ChatGPTを使いこなしているビジネスパーソンは全体の数%程度でしょう。若年層では、宿題や悩み相談のような使い方が広がり、文化を変えつつありますね。一方で、仕事のスピードを劇的に向上させる可能性があるため、活用できる人とできない人の間に大きな差が生まれています。
金森:生成AIを「使っている」という人でも、Google検索のように一問一答的な使い方に留まっている人が多いですね。問答を繰り返してより深めていくことができるChatGPTの利点を生かしていないのはとてももったいないことです。
富士:実際には、生成AIを活用すれば作業効率は大幅に向上します。例えば、私自身、セミナー資料の作成時間が30時間から1時間に短縮されました。単純に計算すれば30倍のスピードです。また、これまでは、Noteへの記事の掲載は3週間に1本のペースでしたが、私が気になったことをChatGPTに質問して、その内容をNote用にまとめてもらうようにもした今では、1日に5本の記事を上げることが可能になりました。仕事でも趣味でも、情報収集や下書きの作成にAIを使うと作業のスピードと精度が飛躍的に向上することを日々実感しています。生成AIは、SNS、教育、ビジネス、エンタメなどあらゆる分野に急速に浸透してきています。もはや「AIを使うか使わないか」ではなく、「どう使いこなすか」が問われているのです。
次のページマーケティングにおける生成AIの活用方法
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
インサイトナウ編集長対談
2024.06.03