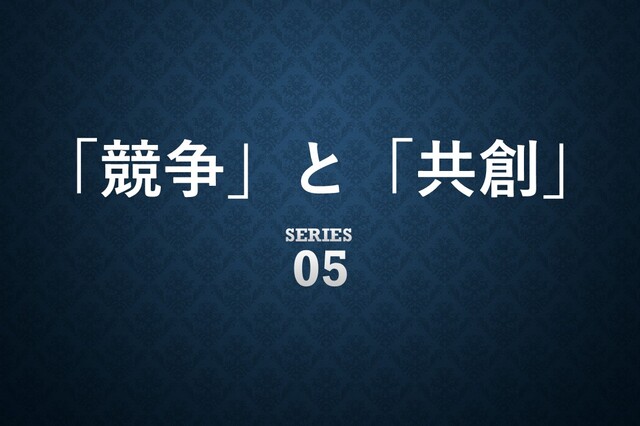/外国人観光客だの、国内富裕層だのは、調子が良いときだけの「御大尽」で、被災地になったら、見向きもしてくれなくなる。いくらかつての馴染みだろうと、彼らが善意のボランティアとして駆けつけ、いっしょに手足を泥だらけにして復興を手伝ってくれる、などと期待できるわけもあるまい。/
儲け話に飛びつくのも、わからないではない。しかし、物事は短期(一年未満)・中期・長期(十年以上)でリスク査定して、そのメリット・デメリットを評価してみないと、良し悪しはわからない。
世界的なコロナ禍も終わって、日本の円の急落もあって、四千万人近い訪日外客が押しかけてきている。国内の日本人も、勤め人、パートやバイトが物価上昇で困窮する一方、資産家や経営者は、富裕層として、時間をかけた宿泊旅行にケタ外れの浪費も厭わない。これに乗じて、有名な観光地はもちろん、とんだ僻地まで、彼らの誘致に目の色を変えている。
が、どうなのだろう、能登の復興の遅れは。まったくと言っていいほど、進まない。神戸や東北も、ここまでひどくはなかった。その元凶の一つに、能登の経済が観光や高額の工芸品・海産物に大きく依存していたことがあるのではないか。大量の観光客がつねに押し寄せ、これらに大金を落し続けないかぎり、カネが回らない。もっと厳しい言い方をすれば、実需の無い高級テーマパークのような経済構造になってしまっており、人が来なくなったら、血も通わなくなってしまった。いくら地元の人が困窮しようと、これでは、これをなんとしても復興しようという世間の機運さえも起こらない。
戦後の焼け跡でもそうだったが、被災地で最初に必要になる産業は、被災者の、そして、復旧に訪れた作業員のための日々の食事の提供だ。それは、法外な価格の豪華なカニやエビなどではなく、当たり前の、しかし暖かく、心も休まるドンブリものや定食。そんな安い店に人々が集い、新たな仲間と出会い、まだよく見えない明日を語り合う。そここそが、復興の原点。
その次は、そこから地元の自営業や中小産業が自力で再生すること。もちろん、田畑や港湾、工場も被災するだろうが、地元を思う人々の固い意志は、驚くほど強い。どうにもならないと思えるような瓦礫の山でも、手で、重機で片づけていけば、一年もあれば更地になる。たしかに、広域サプライチェーンに依存する、以前のような複雑なビジネスは、人脈も寸断されてしまっていて、困難かもしれない。しかし、町工場の小産品、果物や干し物、ビン詰めやカン詰めのようなものであれば、地元の人々の雇用も生み出し、商品を都会の消費地に売り出して、全国の一般の人々の善意と支援を仰ぐことができる。
ようするに、外国人観光客だの、国内富裕層だのは、調子が良いときだけの「御大尽」で、被災地になったら、見向きもしてくれなくなる。いくらかつての馴染みだろうと、彼らが善意のボランティアとして駆けつけ、いっしょに手足を泥だらけにして復興を手伝ってくれる、などと期待できるわけもあるまい。
百日一考
2024.03.22
2024.04.07
2024.10.16
2025.01.03
2025.01.14
2025.01.18
2025.02.16
2025.02.27
2026.01.02
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る