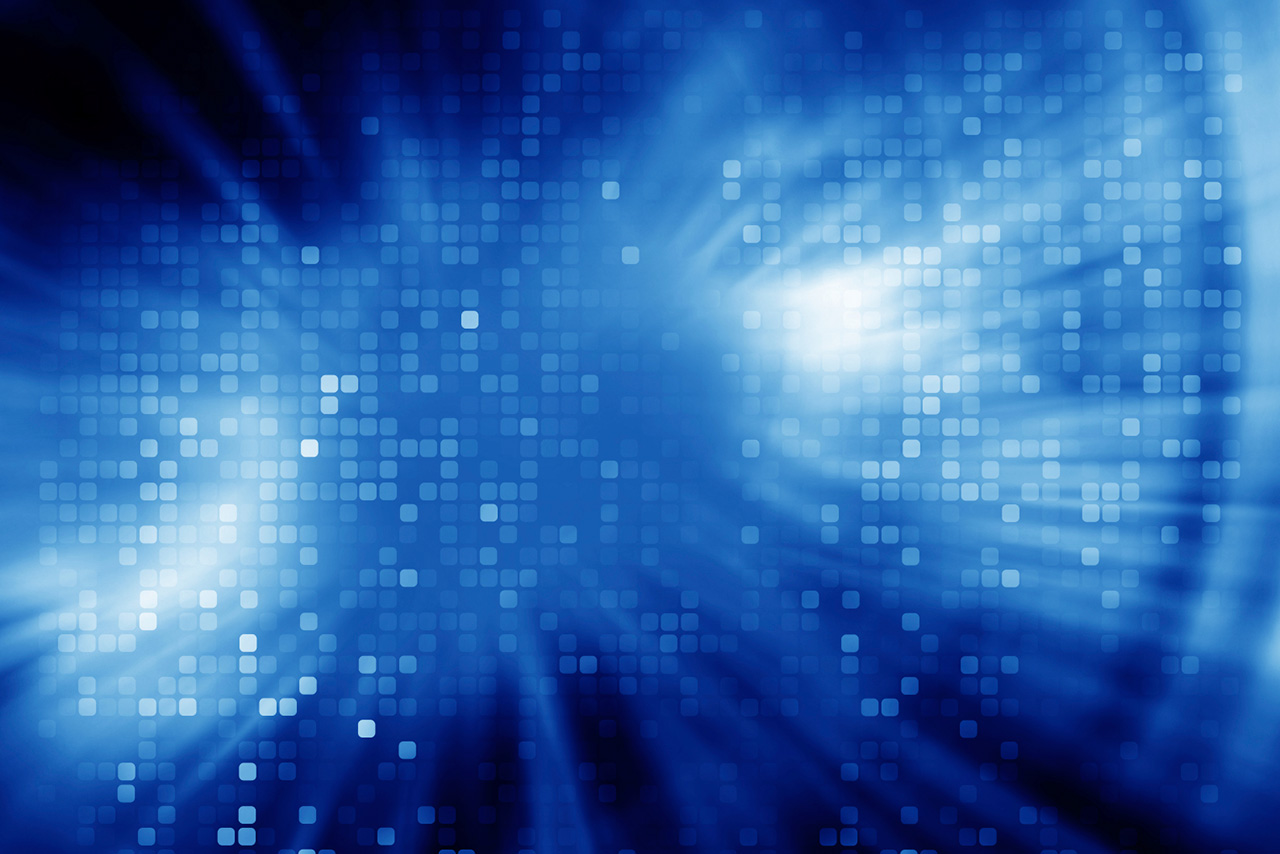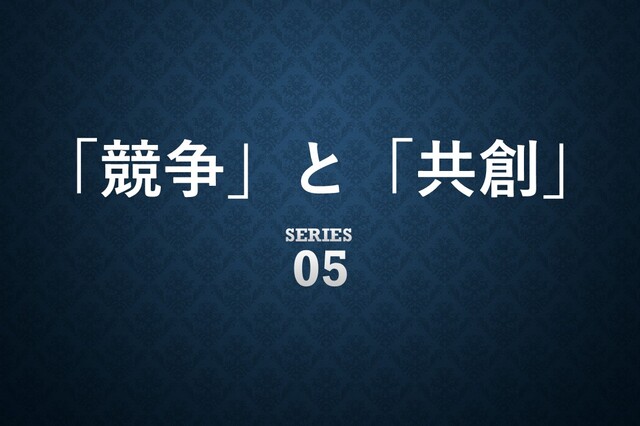2025.11.25
日本は本当に人手不足なのか? ―日本人が、対峙すべき現実―
齋藤 秀樹
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
本当に「人がいない」のだろうか。 それとも・・・ 「人はいるのに、立ち上がれないでいる」のだろうか。 この違和感から、話を始めたい。
- 企業は「余裕がないから」「辞められたら損だから」と、教育費を削る。
- 個人は「学んでも給料も仕事も変わらない」と、仕事以外では学ばない。
こうして出来上がるのは、
「学ばないまま何とかやり過ごすことが、社会の標準モード」
という現実だ。
ここで、一つ問いを置きたい。
あなたの会社は、ここ5年で
「人への投資」と「設備・システムへの投資」、どちらをどれだけ増やしてきただろうか?
設備やITには億単位で投資するのに、人材育成には「研修費が高い」と渋る――
そんなアンバランスが、どこかで起きていないだろうか。
4.未来を信じられない18歳たち
さらに、これから社会に出てくる若者たちの“心”を見てみる。
日本財団が行った6カ国比較の調査では、「自国の将来が良くなると思う」と答えた日本の18歳は15.3%。
中国やインドでは7〜8割が「良くなる」と答えているのに、日本だけが極端に低い。
通学電車の中。
制服姿の高校生が、ニュースアプリを眺めながら小さくため息をつく。
「年金はもらえないかも」
「物価は上がるけど給料は上がらないらしい」
「日本オワコンって、みんな言ってるし…」
厚労省のデータでは、10代・20代の死因の第1位は依然「自殺」であり、
その率はG7の中で最悪水準だ。
大人は学ばず、未来に希望が持てない若者が増え、その一部は生きること自体を手放してしまう。
この状況を見て、本当に「人手不足」という言葉だけで済ませられるだろうか。
5.日本人は「個が弱い」のではなく、「場の影響が強い」
ここで、日本人の国民性を少し掘ってみたい。
欧米では、
まず「自分」があり、その集合としてチームや会社がある。
対して日本では、
「場の空気」や「周りの目」の中で、自分が形づくられることが多い。
- みんなが黙っていれば、自分も黙る。
- みんなが残業していれば、自分も帰りづらい。
- 新しいことを言う人が浮いているのを見れば、「自分はやめておこう」と思う。
つまり、
日本では、「個の強さ・弱さ」よりも「どんな場にいるか」のほうが圧倒的に影響力が大きい。
この性質が、悪い方に振れたのが今の姿だ。
- 「どうせ変わらない」という空気が職場を覆うと、
その場にいる全員の「変わろうとする意志」が削られる。 - 「出る杭は打たれる」メッセージが若手に届くと、
彼らは自分の可能性ではなく「無難さ」を選ぶようになる。
その果てに現れるのが、
- 仕事の中で静かにスイッチを切る「静かな退職」
- 社会とつながる意味を見失うニートやひきこもり
なのではないか。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
経営者よ、コミットせよ!
2008.04.29
2008.03.18
2008.02.05
2023.10.24
2025.11.25
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る