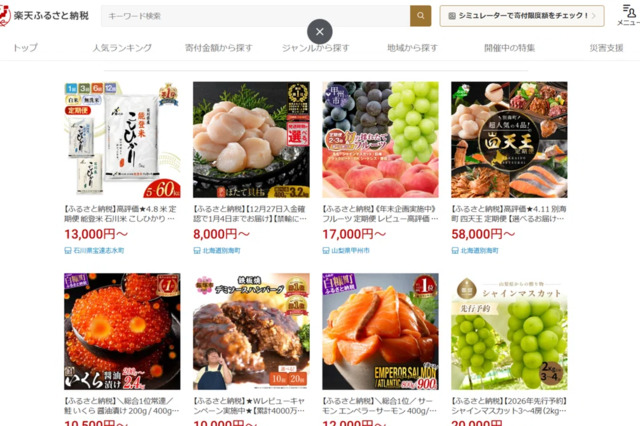ふるさと納税が多くの自治体を地域活性化に本気で取り組ませた効能は大きい。しかし一方で、真の経費率の大きさが5割近いという運営体制や「お得感」だけが追い求められている実態など、制度の歪みは放置すべきでないところまで来ている。
しかも高額納税者ほど恩恵が大きいという点は当初から批判の的だった。それに忘れてはならないのは、これは「ゼロサムゲーム」だということだ。つまりふるさと納税で地方に移転する税金は、元々当該住民が住んでいる都市が住民サービスやインフラ整備等のために充てるはずだったものだ。
いわばこの制度は、都市部の自治体から地方の自治体への富の移転を、政府の代わりに市民自らの選択によって行わせるものなのだ。当然、都市部では財源が不足し、住民が享受すべきサービスはその分削られるのだが、自分のふるさと納税額について嬉々と語る住民にその因果が伝わっているとはとても思えない。
つまり地方の活性化に果たしている貢献度は十分に認知すべきだが、ふるさと納税の制度の歪みは放置すべきでないところまで来ており、見直しの節目にあると小生は考える。では具体的にどうすべきか。
まずは最低限でも、経費率を3割程度以下に圧縮することが必須だろう(地元産業に付加価値が残る「調達費」の割合については今のままでいい)。そのため地域自治体同士で連携して、仲介サイトに全面依存しない体制を築くための効果的な方策を研究すべきだ。
具体的には、共同事務センターを作る、仲介サイト間での競争を煽る、寄付してくれた利用者に直接コンタクトして次から直接寄付してもらうよう働き掛ける(この場合、何かおまけをつけてもいい)、などが考えられる。
また、利用者にも意識変革を促す施策を考えるべきだ。例えばある金額以上(10万円以上など)のふるさと納税利用者には1割以上の金額の「返礼品なし」の寄付を義務付けるのはどうだろう。つまり「本当の寄付」を1割しないと税金控除にならないようにするのだ。しかもこの「返礼品なし」寄付先対象には地元(つまり都市部)自治体も含むとしてはどうだろう(今のふるさと納税は地元自治体に対しては原則として不可)。
事務手続き的には少々面倒になるが、市民の意識変革にはインパクトがあるはずだ。今の「お得な通販ショッピング」感覚一本やりから、本当の寄付はどうあるべきかを考えてくれる人が増えるのではないか。
そして地元にどんなNPOがどんな活動をしているのかを知ることで、ふるさと納税とは別に直接寄付することも考えてくれたり、「手伝ってみようか」という気になったりすることもあるかも知れない。
その結果、自治体に押し付けるばかりではなく、住民ができること・すべきことに市民が気づく可能性が高まることを期待できる。それは回りまわって都市部の自治体のサービス負荷を減らして、住民同士が助け合いによってカバーするという、本来の「自治」の姿に近づくことにもつながるのではないか。
日沖 博道(ひおき ひろみち):パスファインダーズ株式会社 代表取締役、経営戦略研究会「羅針盤倶楽部」コーディネーター&アドバイザー。
社会インフラ・制度
2023.06.14
2023.09.19
2023.10.18
2023.11.22
2023.12.20
2024.01.17
2024.03.27
2024.06.19
2024.09.18
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る