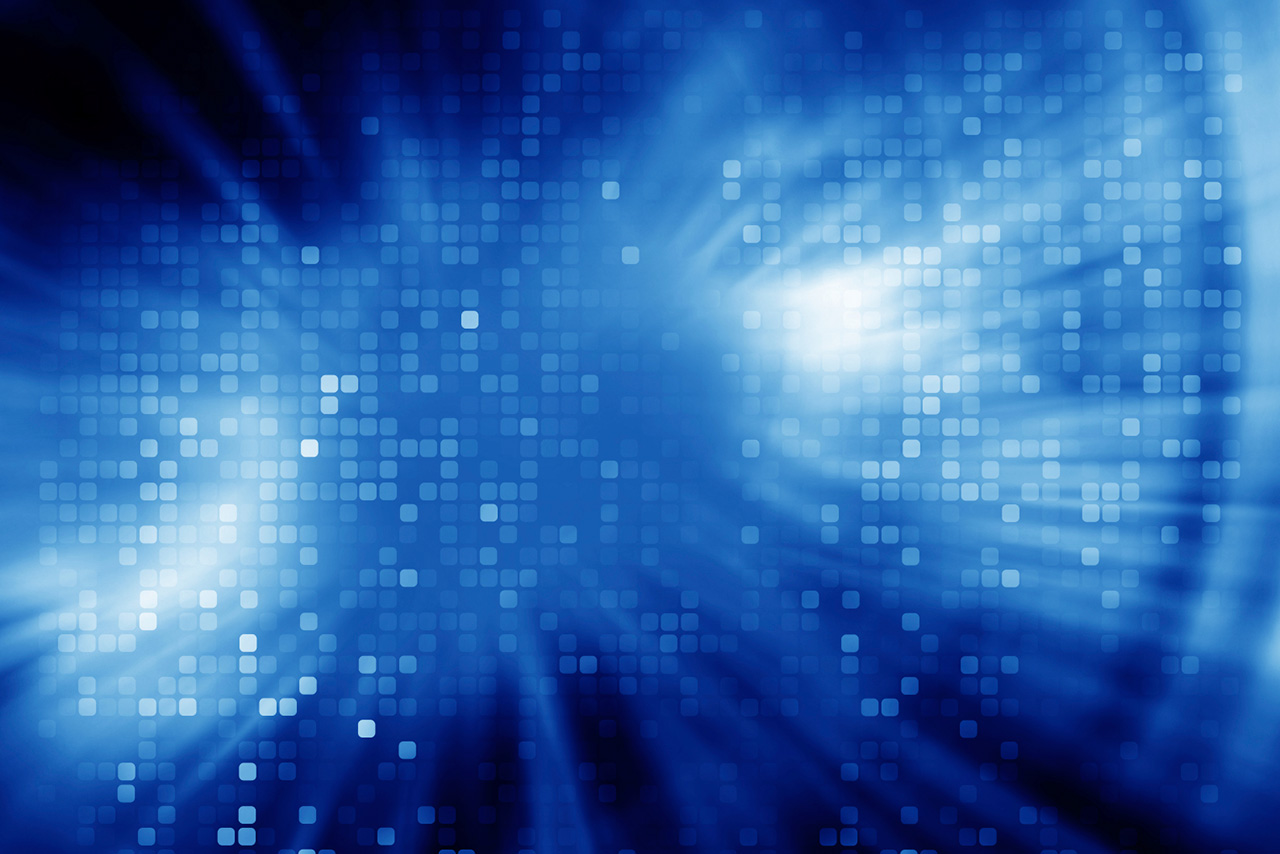企業向けコンピュータソフトを販売するアシストは、社長がビル・トッテンという元アメリカ人(2006年、日本へ帰化)であるために、一見“外資系”のように思われるかもしれない。しかし純粋な日本企業であり、社長みずからが「日本式経営」、つまり戦後の日本で多く見られた終身雇用制度による愛社精神の醸造を企業の安定の要だと喧伝してはばからない会社だ。
そのため普通の会社ではあまり見られないことが起きる。例えば、ある社員が辞めたいといえば、普通なら引き留め、しかし一度辞めてしまえば付き合いはなくなるというのが一般的だが、アシストはその逆で、辞職したいといってきたら基本的に引き留めることはない。トッテンいわく「会社の都合でその人の自由を奪うことだから」。
その代わり、戻りたい、と言ってきたら、その人を受け入れたいという部署があれば再入社が可能である。可能というよりも実際約800人の社員のうち30人が、そのようにして会社に戻ってきている。古市靖もその一人だ。
古市は1992年、新卒で入社して以来10年間アシストで営業マンとして働いた。IT業界で営業の経験を積んだ古市にヘッドハンターの声がかかったのは2003年8月だったという。
「仕事に不満はなかったし、給料だって特別少ないと思っていたわけではないけれど、年収を聞かれて答えると、“少ない!その倍はもらえる”と言われて、そう言われたら、えっ、そうなのか、と(笑)」
こうして古市はアシストを辞め、日本市場に参入しこれから拡大を目指すという、ある外資系IT企業に転職した。しかし働き始めて数日のうちに、雰囲気がまったく違うことに気づいたという。
「とにかくアメリカ(本社)の言われた通りにしなければいけない。さもなければクビ。アシストでは、“お客さんにとって何がベストか”を考えながら営業していたのが、急に“目の前の売り上げ”という、数字ありきの毎日。一応チームという名目にはなっていても、個人の競争」
「それが外資スタンダードなのかもしれないけれど、お客さんの都合よりもむしろ、こちらが売らないといけないタイミングに合わせる強引さが必要になる。タイミングが合わなければ、次のお客さんにいかざるを得ない。そうなると、お客さんを大事にして関係を育てていきたい気持ちとは裏腹に関係性は少しずつ希薄になる。お客さんと長い時間軸で誠実に接し続けることが営業方針であった自分に嘘をついて、このまま仕事を続けることはできないとすぐに思った」。
お客さんにもっとも適した製品を最善の条件で提供することを使命として10年間営業をしてきた古市にとって、外資系企業の営業スタイルは、自分の心に、“不誠実”な場所だった、と振り返る。

「月給は2倍になったけど、社内でも足をひっぱりあって、こうしてずっと競争し続ける、それが一生の自分の仕事だと思うとつらかった。僕は心が弱いのかもしれないけど、もう無理だと」。こうしてアシストを辞めた時の上司だった坂本昌史に電話をかけ、アシストに戻りたい、と相談をする。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
株式会社アシスト
2011.03.04
2011.02.03
2010.12.22
2010.12.13
2010.11.19
2010.11.09
2010.10.15
2010.09.11
2010.08.19