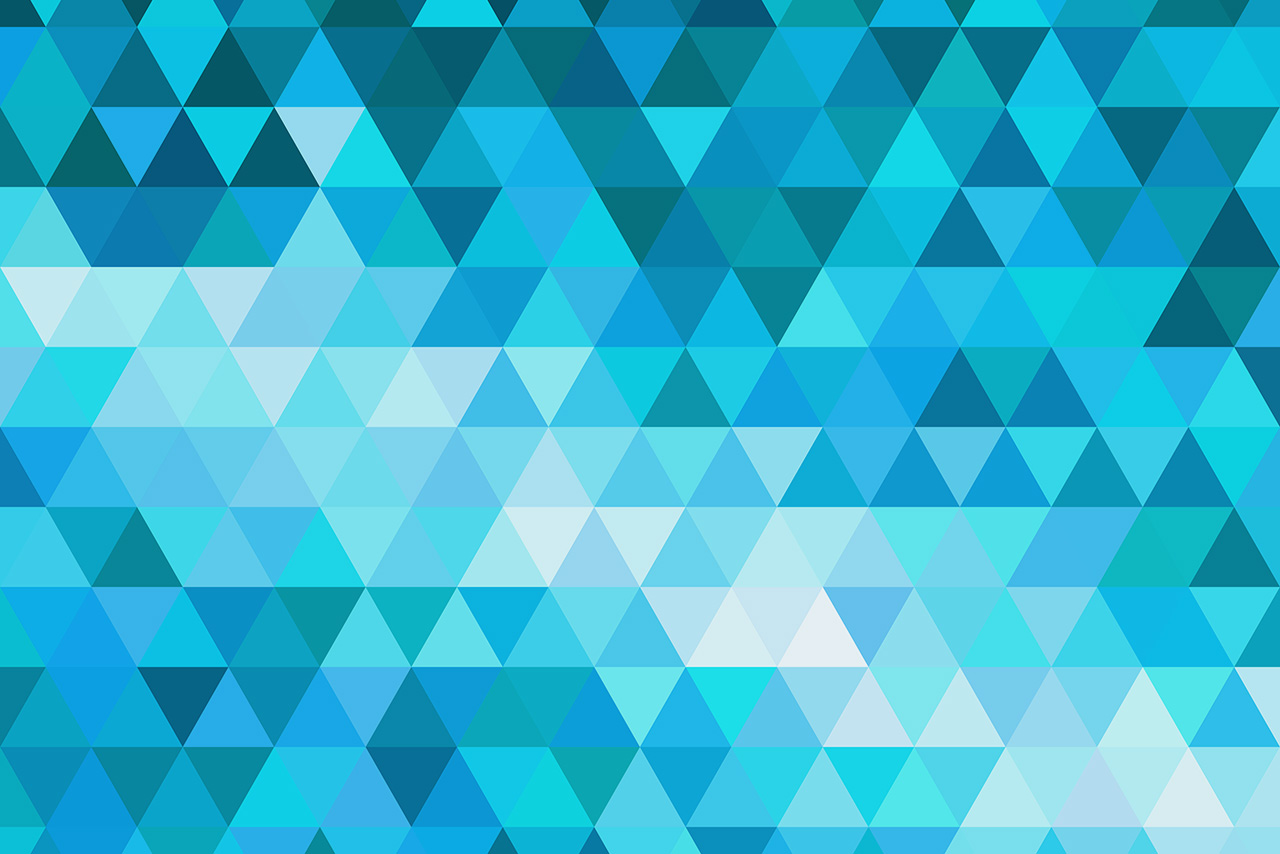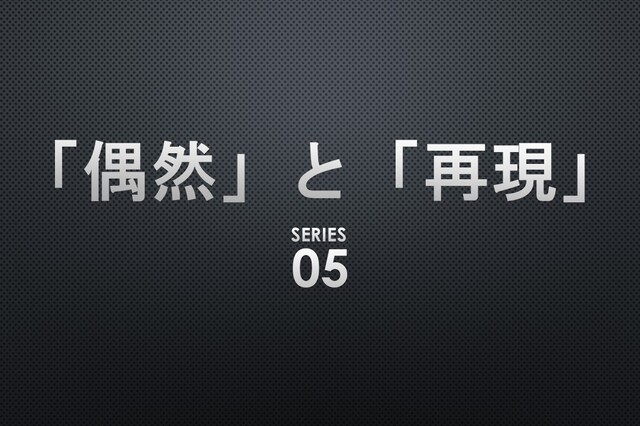「ファシリテーション」という言葉、感度の高いビジネスパーソンであればもうチェック済み…と思いきや、言う人によってその定義はまちまちで、良くいえば百花繚乱、悪く言えば玉石混淆。 この新しいコミュニケーションスタイルをマスターするために、誰でも必ず押さえておきたいスキルマップとは… -・-・-・-・-・-・-・-・-・-
なんて言ってると、「人前で話すこと、あんまりないから自分には要らないかな」なんて思う人もいるかもしれないんですが、ちょっと違うんですね。
というのは、リーダーに必要とされる役割って、時代とともに変わってきていて、「人前で話して納得と共感を得るスキル」は、今や誰にでも求められているのです。
たとえば、MBAや論理思考など、90年代末からでしょうか、一世を風靡して、「MBAを勉強すれば、幅広い知識に基づいた緻密で間違いのない意思決定ができるんだろうな」と思いがちですが、いわばこれは「冷たい」リーダー像。
ところが、マネジメント教育の本家にあたる欧米では、リーダー像は変わってきていて「冷たい」リーダーはむしろ過去のもの。最近では、グチャグチャな状況の中でも人々に目指すべき方向<ビジョン>を示す、そのビジョンに多くの人に共感・賛同<コミット>してもらう、そのために自分の想いを熱く語る、など、「熱い」リーダー像が必要という流れになっています。
たとえば、ひところ日産を率いたカルロス・ゴーンさんもそうだったかもしれませんし、20世紀の名経営者と言われるGEのジャック・ウェルチ氏も、「一緒にいると、エネルギーをもらえる」なんて評価を多くの人から聞いたことがあります。
と、ここまで来ると、実はファシリテーションというのは本当は多くの人に必要とされるスキルであるのがお分かりいただけるのではないでしょうか。閉塞感あふれる今のビジネス環境で新たなブレークスルーを見つけるため、あるいは、それこそ企業変革ではありませんが、右肩下がりになってしまった会社をドラスティックに生き返らせるためには、「熱い」リーダーが必要不可欠と言うことなのでしょう。
ひょっとすると、日本人が苦手とする分野で、上記のゴーンさんやウェルチさんの例を出すと、「ああ言うカリスマみたいな人は生まれながらにしてできる」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。むしろ、出来ないとしたら、単に練習したことがないだけ。
だって、良く分析してみると、カリスマのような話し手でもやっていることは意外と単純。
・自分の想いをストーリーにして多くの人に共感させている
・人によってコミュニケーションスタイルは異なることを
理解して、最適なモードを選んでいる
・難しいコンセプトをたとえ話を使って説明している
など、一つひとつの要素に分解していけば、身につけることはできるものです。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
ビジネスファシリテーター
2011.01.21
2010.09.01
2010.08.09
2010.05.17
2010.04.02
2010.03.23
2010.03.15
2010.03.08
2010.03.04