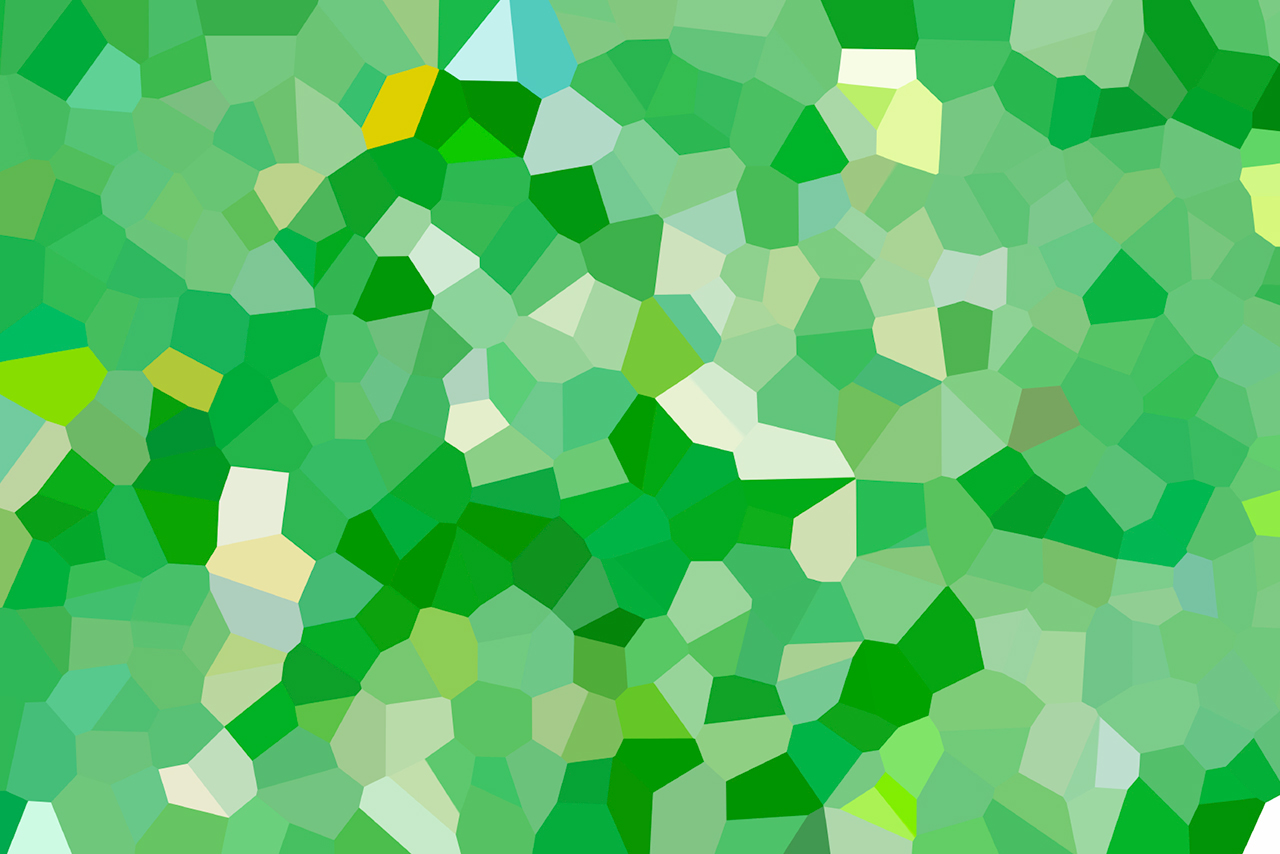北の都・札幌は冬場、どか雪に悩まされる。降り積もった雪を溶かす融雪装置だが、従来のものはムダの多さが欠点だった。「何とかムダをなくし、環境ダメージを抑えられないか」。エコで北海道を良くしたいと願う若手社長の熱い思いが生んだ画期的な装置が『ゆりもっと』だ。

第二回
「一冊の本が開いた新しい進路」

■ケータイと出会い、ケータイを学び、極める
「とにかく音を売って来い、と。これがクリプトンで僕に任された仕事でした。オリジナルの音源を提供して、携帯電話のコンテンツ、具体的にいえば着メロなどで使ってもらうわけです」
今でこそケータイには最初からいろいろな着メロが入っている。また自分の好きな曲をダウンロードして使うこともできる。しかし、ここで時計を数年分巻き戻して一昔前のことを思い出していただきたい。当初のケータイには着信音でさえせいぜい5種類ぐらいしかなかったはずだ。
「社長の目の付けどころがすごかったんです。いずれケータイが若い人たちに普及すれば、必ず人と違う着信音を求めるようになる。だから最初から携帯電話にいろいろな音を入れておくことがビジネスになるんだと」
モノを売った経験などまったくなかった新人営業マン入澤氏は、飛び込みで携帯電話メーカーに売り込みをかける。時代の波が入澤氏の味方をした。ちょうどi-modeが出て、ケータイの爆発的な普及が始まった時期である。誰もがケータイを持つようになると、特に若者たちはケータイにも個性を求めるようになる。着信音一つとってみても、人と違った音が価値になるわけだ。着信音や効果音での差別化アピールはメーカーニーズにぴったりとはまった。
「新人営業マンだった僕でも、三洋電機さんやソニーエリクソンさんはきちんと話を聞いてくれました。そしてプリセットで音をいれてもらえたんです。なかでも達成感があったのが、ソニーのプレミニですね。あれはかなり画期的なデザインが売り物で、それなら音にも徹底的にこだわろうという話になりました。キーロックを外すときの音まで考え抜いてたとえばジッポーの蓋を開ける音を提案して、それが受けたりと」
こうした携帯電話メーカーとの交渉経験は、後の入澤社長にとって何より得難い財産となる。
「この間にケータイが世に出るまでのプロセスをすべて勉強させてもらったわけです。そこでケータイが秘めているとてつもない可能性に気がつきました」
■私、これ(本)で会社を辞めました
「そんな頃ですね、梅田望夫さんの『ウェブ進化論』を読んだのは。これがまたとんでもなく衝撃的だったんですよ。そうか、アメリカはそんな風に進化しているのかって。僕が頭の中でぼんやりと夢想していたことがすべて、クリアに書かれていましたから」
十代で渡ったアメリカで仕込まれた種は、一冊の本から得た養分でまさにはちきれそうなつぼみにふくれあがった。アメリカにいたとき何となく描いていた未来図が、向こうでは実現されつつある。その動きには必然性があり、やがては日本でも同じことが必ず起こる。入澤氏は確信を持つ。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
FMO第8弾【エコモット株式会社】
2008.05.20
2008.05.13
2008.05.07
2008.04.28