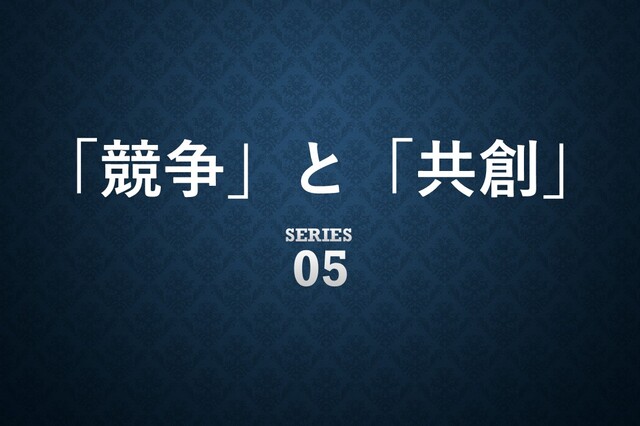「かかりつけ医」は意味も機能もあいまいなまま・・・。
「ロゼトの奇跡」は、アメリカのペンシルバニア州にあった、高齢者が驚くほど健康だった町の実話ですが、20世紀前半に行われた研究は「ロゼトの人々の健康の秘訣(ひけつ)は、連帯感や助け合いにあった」という結論を導きました。近年も、「社会参加する機会が多いほど、死亡率が低い」「誰かと一緒に食事をする機会が多いほど、要介護のリスクが低下する」「友達の数や種類が多いほど、自分の歯の本数が多い」「1人で運動するより、皆で運動する方が効果的である」など、つながりや交流の多さが高齢期の健康のカギであるという研究結果が次々と発表されています。
これらの研究から明らかなのは、健康とは、医療によって実現するというような単純なものではないということです。
確かに、病気やケガを治療して元に戻すのは医療の役割ですが、病気がケガを未然に防いだり、小さな異変や不調に気付いて上手に対応したり、健康維持に配慮した生活を継続するといったことは、医療ではなく、私たち一人一人、また個人を支える家族やコミュニティーの役割です。つまり、プライマリーケアは「医療によるケア」と「コミュニティーによるケア」の2つから成ると理解すべきだろうと思います。
しかし、医療によるプライマリーケアが十分に機能している、つまりどんな地域にも、ほとんどの疾患に対応できる医師が存在し、日常の健康相談などに継続的に乗ってくれるような状態は当面、期待できません。日本にはそれだけの数の「一般医」がいないからです。
例えば、総医師数に対する「一般医」の割合は、イギリスやドイツでは約3割、フランスでは5割近くになりますが(出典:高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研究会報告書【2005年版】)、日本ではそれほどの数はいないとされています。
一方のコミュニティーによるケアも、孤独や孤立が問題になるくらいですから心もとない状況で、つまり、高齢者が適切なプライマリーケアを手に入れるのは相当に難しいというのが現状です。
高齢者の不安、高齢の親と遠く離れて暮らす現役世代が抱く不安の原因はここにあり、元気なうちの住み替えを検討する高齢者や、親の「終の棲家(ついのすみか)」選びを考え始める現役世代が増えているのも、このような現状をよく表しているのでしょう。
高齢社会
2024.11.06
2024.12.23
2025.01.20
2025.02.25
2025.04.14
2025.06.02
2025.07.29
2025.09.17
2025.11.17
NPO法人・老いの工学研究所 理事長
高齢期の心身の健康や幸福感に関する研究者。暮らす環境や生活スタイルに焦点を当て、単なる体の健康だけでなく、暮らし全体、人生全体という広い視野から、ポジティブになれるたくさんのエビデンスとともに、高齢者にエールを送る講演を行っています。
 フォローして川口 雅裕の新着記事を受け取る
フォローして川口 雅裕の新着記事を受け取る