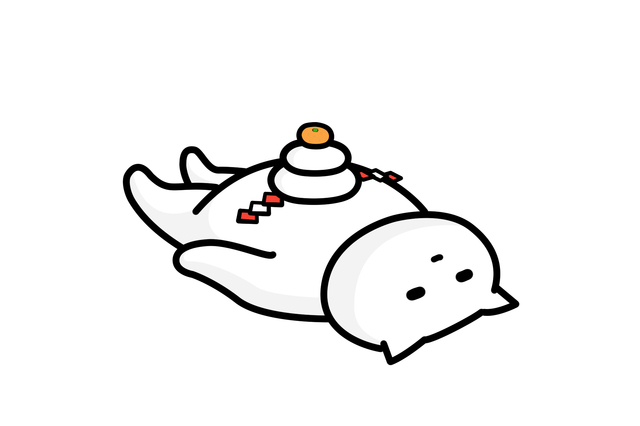/根本にあるのは、生存意志、つまり自己本位の欲で、事実の認識なんて、それに合うように捏ち上げられているだけ。どんな物語(世界)を出してきたところで、どれが「正しい」かは、力づくで強引に決めつけられるだけ。結局、だれかが納得せず、永遠に物語の闘争が続くだけ。しかし、物質的自然そのものも生存意志を持っており、暴力的かつ無目的に歴史を紡ぎ出していく。/
だが、マルクスは、投影的な表象(イデオロギー)論の背景として、フォイアーバッハのようにそれを支える人間集団、階級の存在を考えており、この後、国際労働者協会(第一インターナショナル、1864~76)の政治運動に傾倒していく。ところが、プルードン(1809~65)やワーグナー(音楽家、1813~83)、バクーニン(1814~76)らは、あくまで世界をショーペンハウアーのばらばらな個人的物語の闘争として捉え、個人独立のアナーキズム(無政府主義)を主張し、財産共有をうたうマルクスらのコミュニズム(共同体主義)と対立。労働者協会は内部分裂して瓦解。
一方、自然誌学者ダーウィン(1809~82)は、大英帝国の測量船ビーグル号の世界一周(1831~36)に随行。この経験から、彼は種の多様性に驚くとともに、絶滅種と生存種の関係を体系的に考察。そして、1859年に『種の起源』において提起した生存競争と適者生存の自然淘汰の学説は、通俗化して、脚光を浴びる。おりしも産業革命と資本主義や帝国主義の進展で、企業間、国家間の競争が激化。数十年も前のショーペンハウアーが一躍、再評価されるようになる。
ただし、ショーペンハウアーは、物質的自然の絶対的生存意志を前にして、個々ばらばらの私的な世界の物語など虚妄にすぎず、たがいに争った末に、結局、いずれも無力に果てる、と考えていた。ただ、天才のみが、シェリンクが言うような物質的で精神的な芸術を通じて、自然の生存意志を垣間見るが、それも一時的にすぎない、とする。それゆえ、彼は、インド仏教の影響の下に、個々の生存意志の放棄、自己の無化によってこそ、むしろ自然に全体化する、それが哲学の役目だ、と主張していた。
けれども、デンマークのキルケゴール(1813~55)は、『死に至る病』(1849)において、人間は自分の現実と自分の希望を自分でつなぐ責務がある、それが実存(行動として存在すること)だ、と言う。その人間として生きる責務を放棄し、自己を消して自然になるに任せるなど、魂の死であり、神の救いに背を向ける最低の罪である、とする。アナーキズムのワーグナーと決別したニーチェ(1844~1900)もまた、『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-5)で、生存どころか最後の敗退まで承知の上で、あえて現実と希望を綱渡りして越え出て行こうとする強靭なニヒリズム(虚無主義)、権力意志の運命愛をうったえた。
哲学
2023.05.28
2023.07.18
2023.08.15
2023.10.16
2023.11.23
2023.12.30
2024.03.05
2024.03.14
2024.05.29
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る