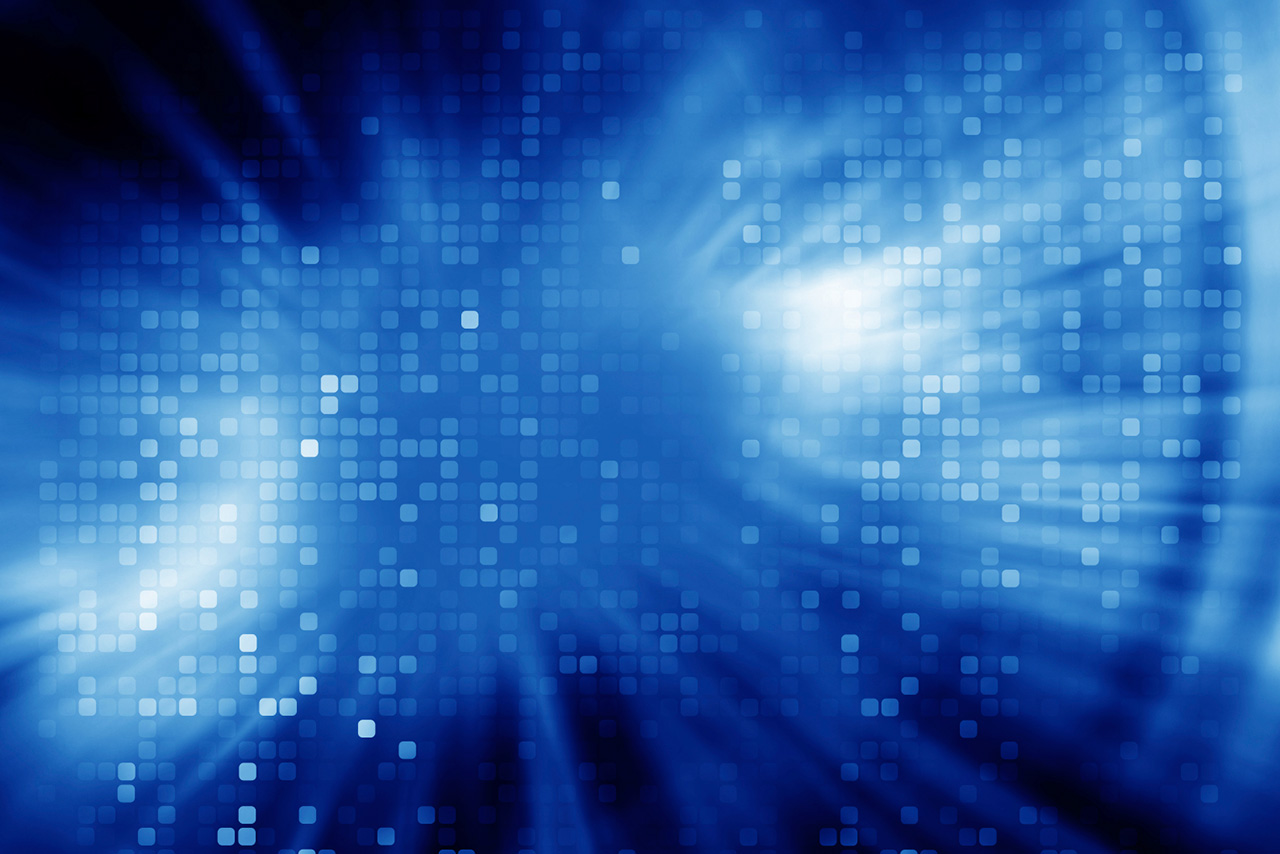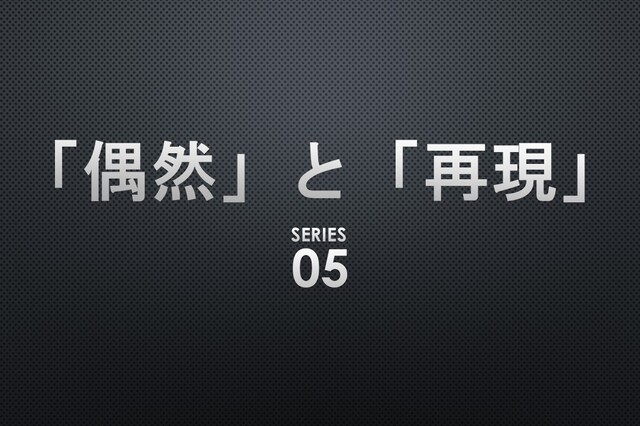企業の社会的責任を考慮した調達のあり方とはどのようなものでしょうか?
企業の調達部門の役割・機能は所謂QCD(品質、コスト、納期)の最適な調達先から最適な調達を行うこと、と言われています。
最近はこれに追加しCSR(企業の社会的責任)調達の推進が非常に重要視されています。これはサプライヤのCSRの遵守状況を確認し、CSRに配慮を行っている取引先から調達を行うというものです。
CSRの観点から言うとISO26000が2010年に制定されていますが、ここでは大きく以下の7点を配慮するように上げられています。
1.CSRの取組
2.人権・労働条件
3.安全衛生
4.環境
5.公正取引・倫理
6.品質・安全性
7.情報セキュリティ
とくに中国等のLCC(ローコストカントリー)からの調達に関しては2.人権・労働条件に関して児童労働や過酷な労働環境などの問題が上げられています。一方で
卑近な例としては「公正取引・倫理」に含まれる『反社会的な勢力との取引の禁止』です。この件については昨年のみずほホールディングスの事案以降、日本企業でも一層配慮を進める動きがでてきています。
また「環境」面では欧州の環境規制だけでなく『紛争鉱物』に関しても対応が必須になっており、対応に苦労しているというのが実態でしょう。
このように調達部門の業務範囲は近年益々広くなり、その一端がこうしたCSR調達の推進によるものであることが理解できます。
しかし、企業の社会的責任という観点で調達・購買を捉えた時に先に上げた7つの事項では大切な何かが欠けているような気がします。私は企業の社会的責任という観点から調達を捉えた場合に、今後より重視すべきことは最適価格の追及であると考えます。
例えば今年の4月より消費税が5%から8%にアップします。昨年の10月1日より
「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されましたが、ここでは消費税の転嫁拒否
等の行為の是正を求めています。アベノミクスでは2%のインフレターゲットが設けられました。また円安による輸入品や素材のの価格上昇、建設工事需要に対する人手不足などから、多分2020年の東京オリンピック開催まで半ばバブルが続くように購入品価格は上昇する方向でしょう。
ミクロの視点で考えるとこういう局面で如何にコストアップを抑制し競合他社に伍していくかが企業の競争力につながります。しかし、歪みが生じているにも関わらず適正価格を追及するのではなく価格のみに焦点を絞った行き過ぎた安価購買の追及をすることは、取引先の経営だけでなく社会に与える影響も少なくありません。
これは大手企業になればなるほど言えることでしょう。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
調達購買コンサルタント
調達購買改革コンサルタント。 自身も自動車会社、外資系金融機関の調達・購買を経験し、複数のコンサルティング会社を経由しており、購買実務経験のあるプロフェッショナルです。
 フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る
フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る