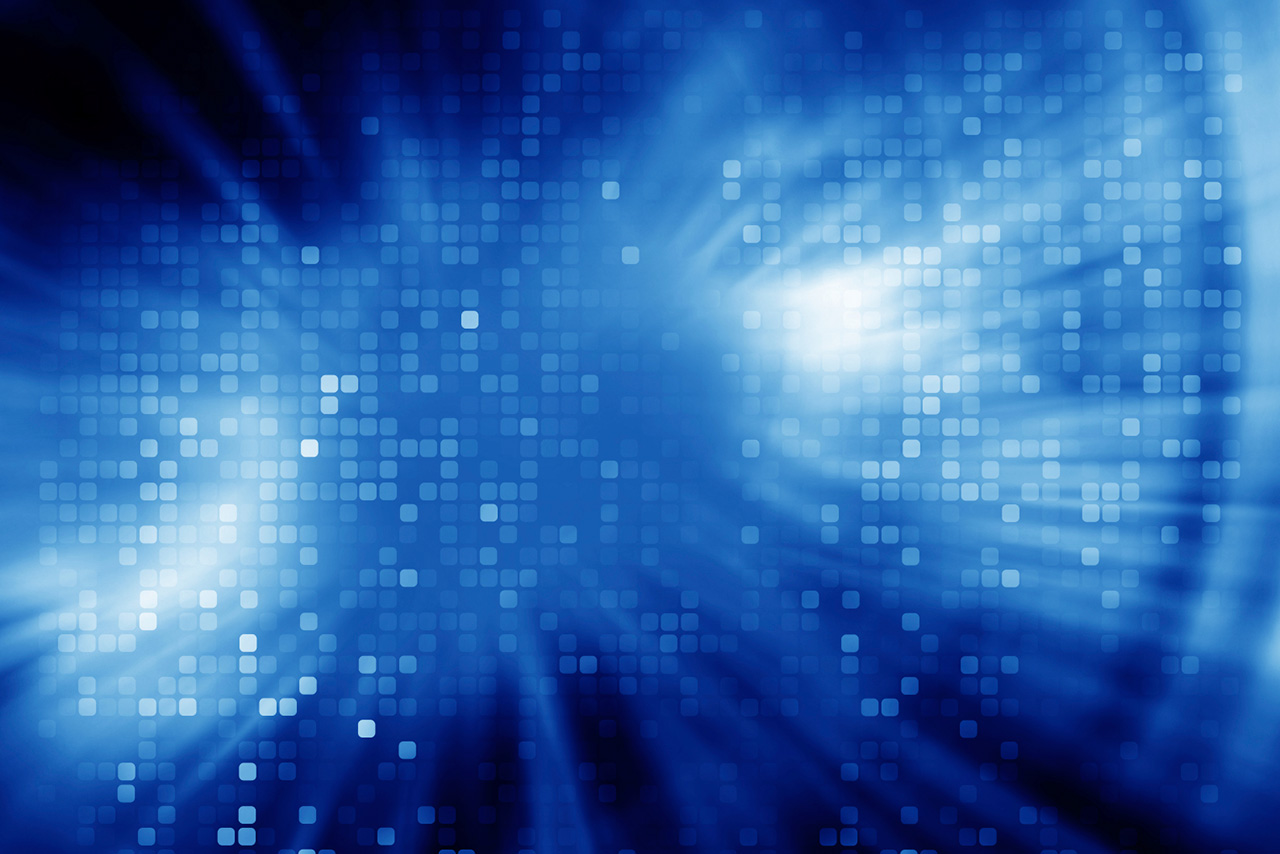改革の際に必ず表れる抵抗勢力。どのように対処したらよいでしょうか?
・・・前の記事より
http://www.insightnow.jp/article/2268
改革には抵抗勢力がつき物です。先に示したように20%の割合で息を潜めて待ち構えているわけですから、その存在を全くないかのように振舞うのは危険です。抵抗勢力には、前もって根回しをしようとか、半ば脅迫的に説得しようなどという対処方法が見られますが、それではマネジメントしているとは言えないでしょう。抵抗勢力がどう出るか分からないので、そのときはそのときと考えていたら、改革に急ブレーキがかかり、そんなはずではなかったと言うこともありえます。チェンジマネジメントでは、この抵抗勢力の影響を予め織り込み済みにして、むしろどのようにそのエネルギーを改革の方に積極的に傾けるかということを考えます。

抵抗勢力と一言で言っても、様々なタイプがあり、これを改革の“チェンジモンスター“と言ったりします。*10)様々な視点があると思いますが、図5は典型的な4つのタイプを示しています。たとえば、「元に戻そう」という勢力が次第に影を潜めるように折込済みにするには、元に戻れるに戻れない仕掛けを作っておくということが奏功するでしょう。「前がよかった」という勢力に対しては、なるべく早期に小さな成功体験を先行して経験させ、より良い新世界を垣間見せたり、前のものを後にした見返りとして説得条件を設けるなどの方法があります。それでは、「どうせ変わらん」、「一息入れる」というモンスターに、あなただったらどのように前もって対処されるでしょうか・・・?
そもそもこれらモンスターの正体は何なのでしょうか?このメカニズムを脳科学的に考えると、大変興味深いチェンジマネジメントの秘訣を探り出す鍵になります。人間の脳には、「前頭前野」と呼ばれる領域があり、新たな変化を理性的に処理する人間らしい機能が備わっています。ところが、その容量と処理能力には限界があり、それを超えるような変化に対しては、不快感や疲労という感情と反応を引き出します。そこで処理できない部分を「大脳基底核」が受け持ち、それが繰り返されるうちに「習慣」が形作られます。変化に対する抵抗の正体は、習慣を変えることに伴う不快感というわけです。ところが興味深いことに、この不快感を他人ではなく自分で解決できたとき、前頭前野にとっては癒しの瞬間となり、プラスのエネルギーへと変質するメカニズムがあるそうです。*11)この体験を、茂木健一郎博士は“アハ体験“と呼んでいます。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
変革を科学する
2008.10.27
2008.10.27
2008.10.27
2008.10.27
2015.07.15
2015.07.24
2015.08.07
2015.08.21
2015.09.04
株式会社インサイト・コンサルティング 取締役
わたしはこれまで人と組織の変革に関わってきました。 そこにはいつも自ら変わる働きかけがあり、 異なる質への変化があり、 挑戦と躍動感と成長実感があります。 自分の心に湧き上がるもの、 それは助け合うことができたという満足感と、 実は自分が成長できたという幸福感です。 人生は、絶え間なく続く変革プロジェクト。 読者の皆様が、人、組織、そして自分の、 チェンジリーダーとして役立つ情報を発信します。
 フォローして森川 大作の新着記事を受け取る
フォローして森川 大作の新着記事を受け取る