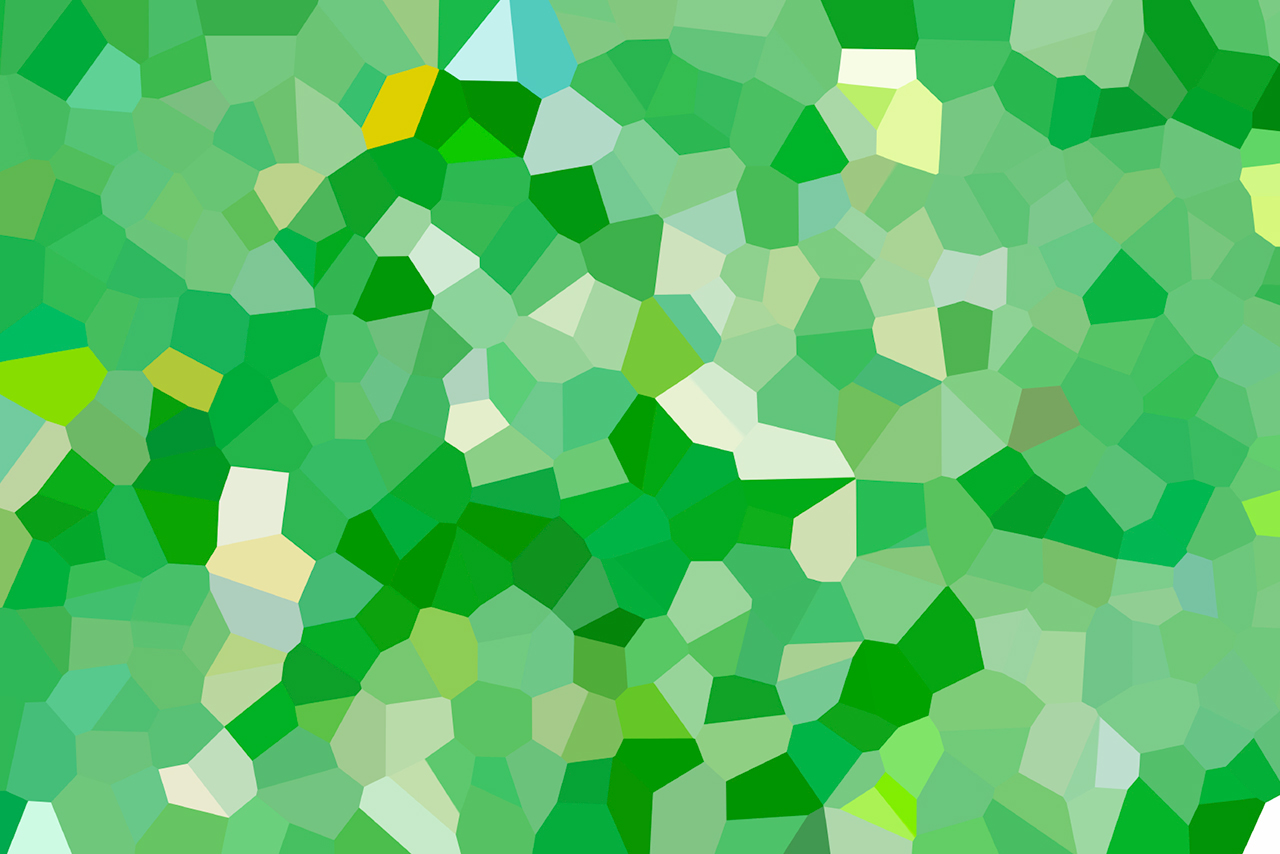奇跡を連発する出版社がある。年間8万冊、一日平均で200冊以上もの本が世に出る中、確実にスモールヒットさせているミシマ社だ。しかも同社は業界の常識を破り、取次を通さず本を流通させている。ミシマ社の一見型破りに見える逆転の発想を探る。
最終回 「本はマーケティングでは作れない」

■本作りのミシマ流哲学
「起業して痛感するのは、読者のほうを向いて、一冊の本としてしっかりと作れば、そんなに大コケはしない、ということです。そのためにも、何よりもまずは、一人でも多くの読者とつながりたいと考えています。それだけですね」
起業以来、数冊のヒット作をミシマ社は世に送り出してきた。著者にはビッグネームも入っている。不思議なのは、なぜそうした著者たちがミシマ社から本を出したのかということ。わざわざミシマ社のような生まれたての、まだ何の力もない出版社に頼らなくとも、彼らには一流出版社からいくらでもオファーが来ているはずだ。現に内田樹氏などは、執筆依頼をいかに断り続けているかをブログで切々と書いている。
「その内田先生が独立しますと言ったら、最初にひと言『書きます』とおっしゃってくださった。ものすごく嬉しかったですね」
もちろん三島氏は、売れなくてもいいなどと思って本を作っているわけではない。とはいえ、売ることが最終目的でもない。わかりにくい言い方になるけれども、一人でも多くの読者に読んでもらえる本を作る。これがミシマ社のポリシーであり、それが「一人でも多くの読者とつながる」ことなのだ。
「僕らは本を作るときにマーケティングなどは一切やりません。こんな読者に、こんな内容の本を、こんなふうにアピールしたら売れるんじゃないか、なんてことはそもそも考えてない」
今のご時世にそんな、ある意味非合理的な考え方で売れる本を作れるのだろうか。
「僕らの方針はただ一つ。おもしろい本を一生懸命に作る。それだけです。ジャンルを問わず、読者を問わず。どんな読者であれ、読みたいのはおもしろい本。これだけは間違いないと信じています」
三島氏のいう「おもしろい」とは何だろうか。実は、ここに本作りの究極のポイントがあるのかもしれない。つまりおもしろさの中身は、各著者の頭の中にしかないのだ。その人が考えているおもしろいことを、何とかしてずるずると表に引っぱり出すのが編集者の役割その一である。そして役割その二は、生のままではまだまだわかりにくいところの残る「おもしろさ」を、多くの人が理解できるように加工することだ。
「著者一人ひとり、それぞれに考えているおもしろいことは違うわけです。だから、その引き出し方、わかりやすく噛み砕く方法、本としての見せ方は一つとして同じものはない。おそらく工業製品の対極に本という商品は位置するんじゃないでしょうか」
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
FMO第13弾【株式会社ミシマ社】
2008.09.02
2008.08.26
2008.08.19
2008.08.12