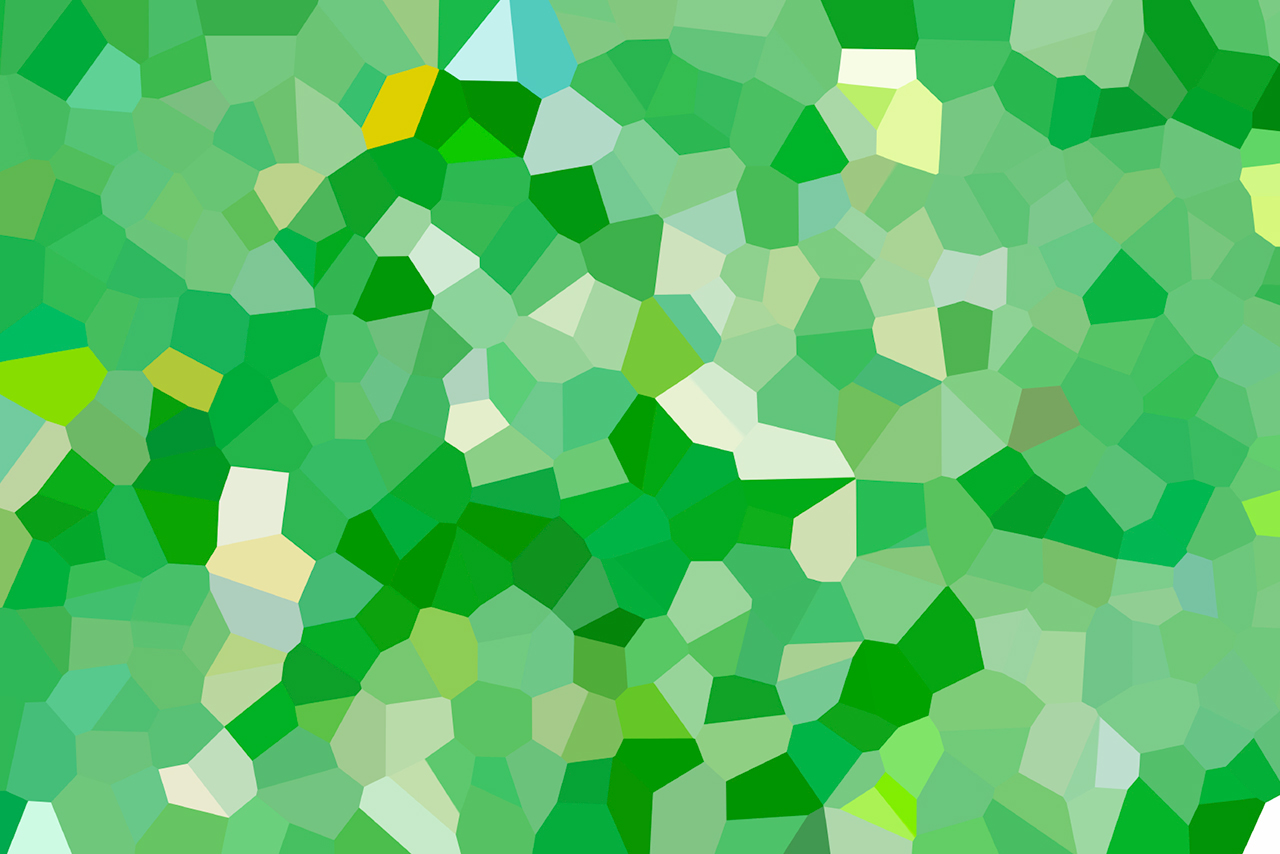奇跡を連発する出版社がある。年間8万冊、一日平均で200冊以上もの本が世に出る中、確実にスモールヒットさせているミシマ社だ。しかも同社は業界の常識を破り、取次を通さず本を流通させている。ミシマ社の一見型破りに見える逆転の発想を探る。

第2回
「真夜中の天啓」

■そうや、自分で作ったらええんや
「革命の空気を吸いたかったんです、なんとなく」
出版社を辞めて一人旅に出た三島氏が向ったのは、東ヨーロッパだった。なぜ、東欧だったのか。その理由は革命の名残を求めてのことだったという。
「もしかしたら、まだ資本主義革命のニオイぐらいは残っているんじゃないかと期待したんです。でも、考えてみれば革命から10年以上経っているわけですからね。街は平和そのもの。のどかなカフェでコーヒーを飲みながら、僕は一体ここで何してるんだっけ、なんて感じでちょっとボケてましたね」
とはいえ閉塞感に苛まれる環境から飛び出したことは、確実に新たな刺激となった。
「どこに行っても、何を見ても、企画が浮かんでくるんです。それこそ次から次へとあふれ出てきて止まらないみたいな。仕方ないからカフェでメモを書きまくっていました。そのときはっきり悟ったんです、僕はすごく編集の仕事が好きで、ずっと本作りをやっていきたいんだって」
編集への思いをぱんぱんに膨らませて帰国した三島氏に、タイミングよく前職の編集長から誘いがかかる。彼は中堅どころの出版社に転職しており、新規事業立ち上げのパートナーにと声をかけてくれたのだ。
「僕のことをわかってくれている人が誘ってくれたんだから、断る理由もないですよね。早く仕事を始めたかったので喜んで行ってみたんですが、オフィスに入った途端、これは合わないって感じました」
巨大企業を親会社に持つその出版社には残念ながら、挑戦心を沸き立たせてくれるような空気がなかった。もっとも元・上司氏は三島氏のそんな反応は計算済み。淀んだ空気をブレイクスルーする起爆剤としての役割を期待していたのだ。
「彼の思惑はわかっていました。だからしばらくがんばってみようと精一杯努力したんです。ところが前の会社と同じテンションで本を作り、手応えもしっかり感じているのに予想を下回る結果しか出ない。そこでわかったのが出版社は編集と営業が両輪でしっかり回っていないとダメなんだってこと。そこはベストセラー経験が少なく、営業がそれほど強くはなかったんです」
方向性の違いばかりはいかんともしがたい。元・上司との関係もあり悩みに悩んだ。床についてもなかなか眠りにつけない。そんなある夜、不意に天啓が訪れたのだ。
「そうや。自分で出版社を作ったらええんや。なんで、こんな簡単な答えに気づかなかったんだろうって」
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
FMO第13弾【株式会社ミシマ社】
2008.09.02
2008.08.26
2008.08.19
2008.08.12