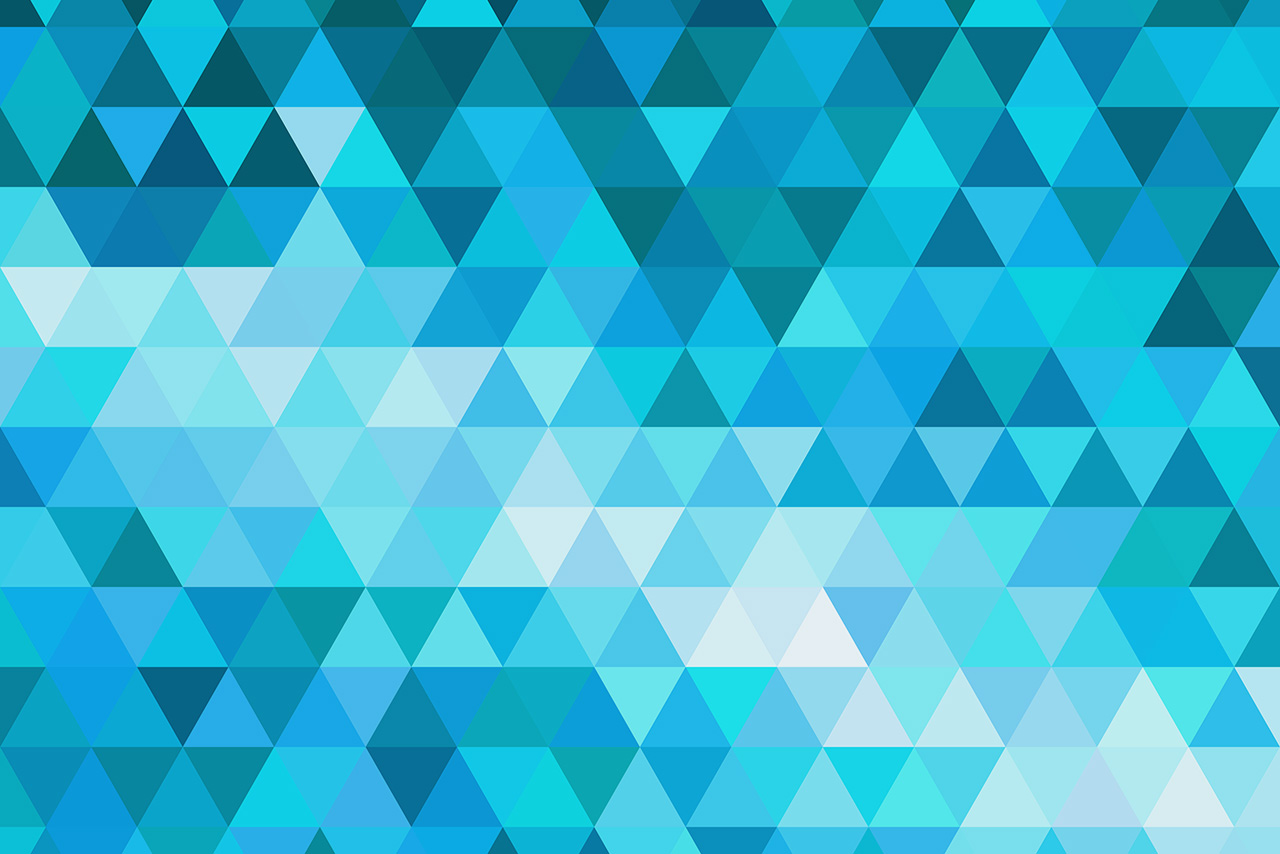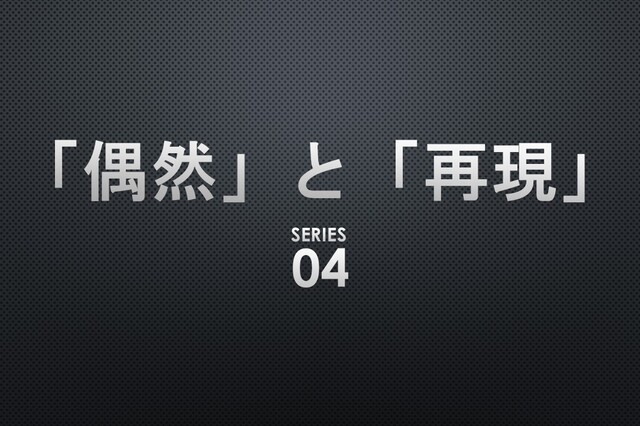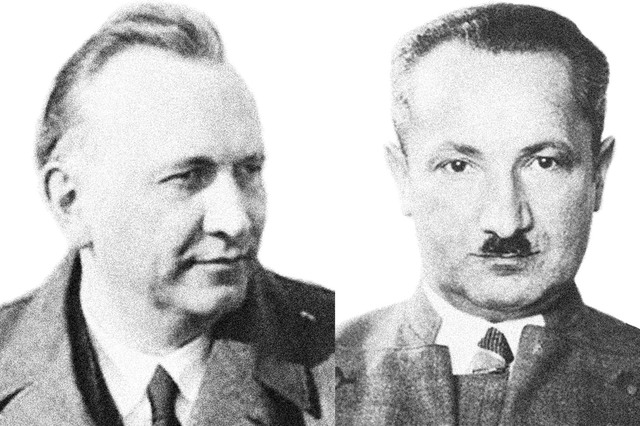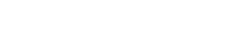突然に降って湧いて出た地方創生は、消費増税を宣告するための布石。地方創生の本質は、住民の奪い合い。何をして地方創生は成功といえるのか?雇用なき成長を実現させるには?第二次安倍内閣の発足から12月までの短い期間で、地方創生を戦略化するには?等々、地方創生の具体案をまとめました
なぜなら、内閣官房(首相官邸の中にあった)地域活性化統合事務局が無くなった代りに、まち・ひと・しごと創生本部が新設されたからです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html
7月15日の毎日新聞によると、自民党行政改革推進本部ワーキンググループは、地域活性化統合事務局を、新設の地方創生本部と合わせて整理・再編する見通しと報じていますから、ほぼ間違いなく、地域活性のための会議体が、まち・ひと・しごと創生本部へ看板を書き換えたと見ていいでしょう。
要するに、地方創生と名称を変えた地域活性は、高度経済成長期から問題提起され続けているにもかかわらず、未だ解決していない、難しい対策です。
如何に難しいか、地域活性を冠した社団法人や財団法人の数の多さを検索してもらえば分かる通り、何十人もの専門家やプロ達が、何十年かけても解決できずにいる難易度ウルトラC政策(それを分っていた石破大臣は、当初、就任を固辞したのかも知れません)
それを数ヶ月そこそこで戦略化しようというのですから、ありきたりで行儀のいい知恵や工夫では、まるで、竹下内閣が全市町村へ1億円を配った「ふるさと創生」のような結末に着地すること必至。
それでも何故、6月に突然、古ぼけた地域活性の看板を下ろし、さも新しそうに地方創生の看板を掲げたかというと、2つの仮説が成り立ちます。
3.【分析2/3】消費税10%増税を年内に決定するための地方創生
一つ目の仮説が、来年、消費税を10%へ増税するためです。
ご存知の通り、来年10%に増税するかどうかの判断を、首相は、年内に決めるとしています。
年内、つまり、突如ローカル・アベノミクスが現れた6月から半年後の12月です。
当初、4月に消費税を8%へ引き上げた後、個人消費は、駆け込み需要の反動で、6月まで下落するものの(実際に下落し、4月~6月期の実質GDPはマイナス7.1%)、
7月以降は持ち直し、秋には回復すると予想されていました。おそらく、安倍総理は、その見込み報告を信じて、昨年、8%増税を決めたのでしょう。
ふたを開けてみれば、アベノミクスで景気は回復したと政府が泣けど叫べど、7月の家計調査や家計最終消費支出を引き合いに出すまでもなく、実際、個人消費は落ち込み続けていますから、
このまま12月を迎えた時、良いデフレの影響による好景気を実感できそうなメドが立っていなければ、とてものこと、増税には踏み切れません。
次のページ4.【分析3/3】来年の統一地方選を意識しての政策
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13

成田 一夫
株式会社たまゆら 事業部長
株式会社たまゆら 事業部長。 「雇用問題を解決し社会に貢献する」をコンセプトにした「いいネしごとぎやフランチャイズ」の本部を統括。
 フォローして成田 一夫の新着記事を受け取る
フォローして成田 一夫の新着記事を受け取る