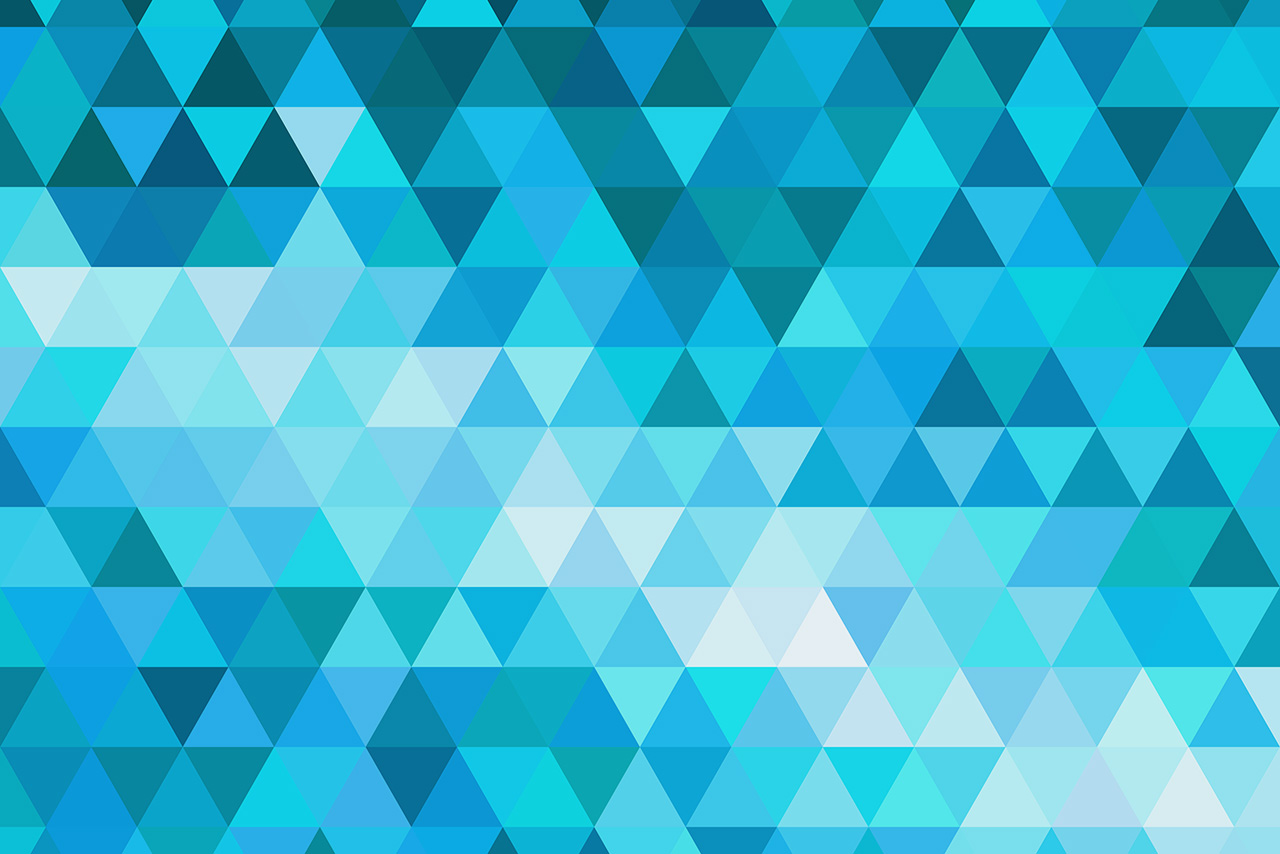ビジネスパーソンは転職を繰り返し、自分に合った職場を見つけた方がいいのだろうか。「雇用流動化をもっと進めるべき」という人もいるが、この言葉の裏に潜む“本音”も忘れてはいけない。 [吉田典史,Business Media 誠]
結局、女性はこの“雇用流動化”の言葉を真に受けて、辞表を書いた。彼女は、自らが契約社員であるのか、それとも正社員であるのかも分かっていなかった。入社時に労働契約書すらなかったという。人事評価もなければ、就業規則もない。残業をしても、残業代は支払われない。こういう中で3年目を迎えようとしたときに、引導を渡された。
そして5年ほど後に、ここのプロダクションに出入りする知人からこんな話を聞いた。「(プロダクションの)社長の兄が経営している会社が経営破たんした。その借金を弟である社長が肩代わりをした」。つまり、女性はふがいない兄弟のしりぬぐいをするために職を奪われたともいえる。
冒頭で述べたコンサルタントに、わたしはこの話をした。しかし、リアクションがない。それも無理はない。一流と言われる人事コンサルタントは、取引をする会社の大半が上場企業と外資系企業である。接点を持つのは部長や本部長クラス、せいぜい人事課長だ。現場の非管理職はもちろん、部課長とも会わない。これは、わたしが出入りする大企業の人事部で聞く不満とも取れる話である。あえて言うまでもないが、中小零細企業との接点は全くない。だから、こういう事例を聞いても想像すらつかないのだろう。
しかし、出版界の末端ともいえるデザインプロダクションや編集プロダクションでは、これに似た事例はありふれたことだ。この業界以外でも、社員数が50人を切る会社を取材すると、よく耳にする。
ここで、わたしは「零細企業の経営者の行為は不当」として騒ぐつもりはない。だが、自らのふがいなさを「雇用流動化」という言葉を持ち出し、覆い隠そうとする経営者がいることは伝えたい。
免罪符をつかんだ、中小零細企業の経営者たち
もう1つの事例を紹介しよう。8年ほど前、赤坂のテレビ局に人材(ディレクター)を派遣する会社(社員数40人)があった。ここが求人広告を出したところ、意外にも主要出版社の編集者(20代後半男性)がエントリーをしてきた。その男性は「学生時代から映像の仕事をしたかった」という。
彼はもしかすると、潜在能力が高いのかもしれない。だが、正社員として採用することには慎重でなければならない。30歳を目前に活字から映像という、その特徴がまったく違うメディアに移るのは、キャリア形成という観点から見てリスクが高い。実際、このパターンで転職が成功する人は、わたしの20年ほどの観察ではほとんどいない。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.10.25
2010.11.12
 フォローしてITmedia ビジネスオンラインの新着記事を受け取る
フォローしてITmedia ビジネスオンラインの新着記事を受け取る