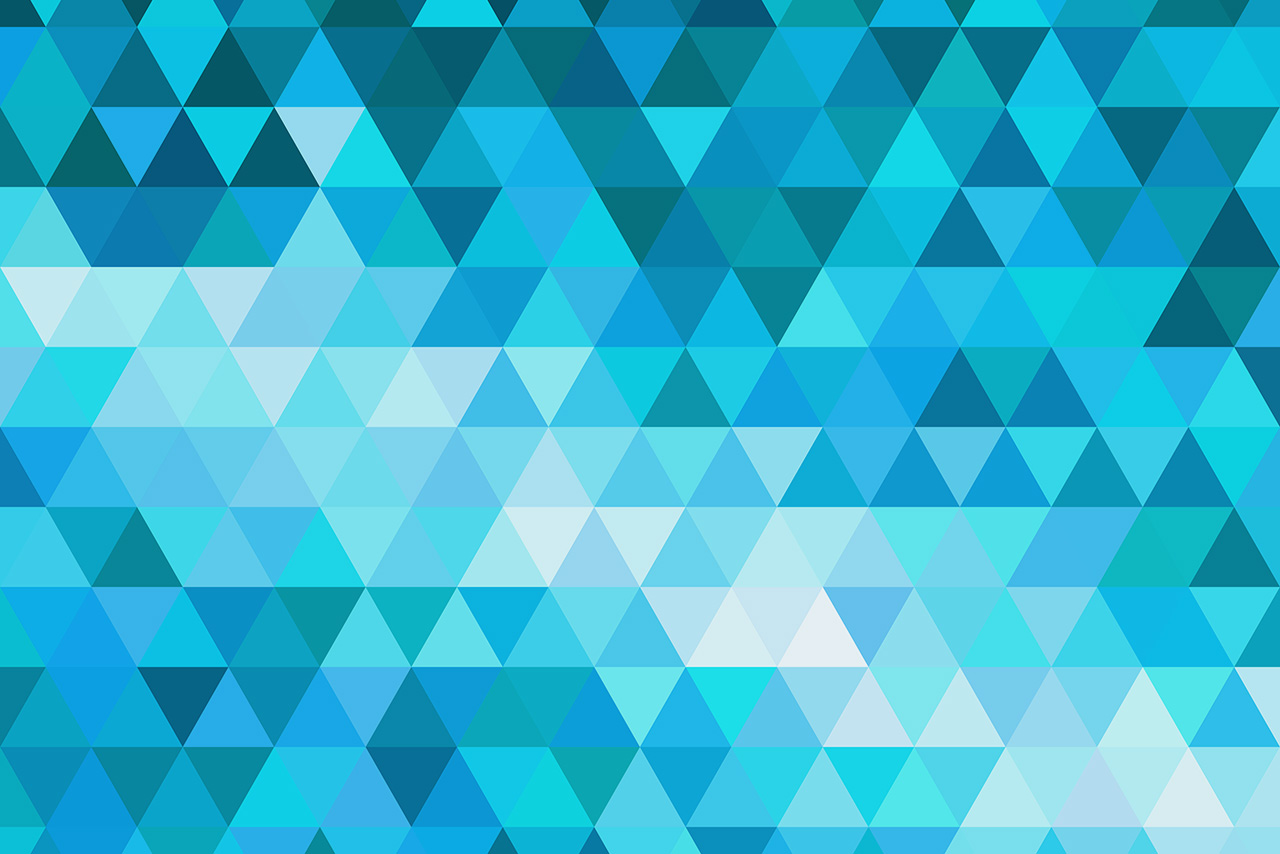部課長が客観性に留まって指示・命令・評価しているだけでは部下は動かない。部下は上司とのやりとりで、「正論」より「熱のある話」を聞きたがっている。「評価」より「自分の存在意義」を求めている。「データ」より「意味・やりがい」に耳を傾ける。
③もろもろの振舞いを通して
コミュニケーションにおいて、語るべき内容は発信者側のいろいろな行為によって相手に伝えられます。相手と直接対面しながら口頭で話しをする、これは最もわかりやすい行為の形ですが、対面せずとも言いたいことを伝える形もあります。手紙やメールがそれです。また、話しをしたり、文面で伝えたりといった言語的な形もあれば、無言でつくる顔の表情や真剣になって取り組む背中など、非言語的な形でこちらの気持ちが伝えられることもあります。
そのようにコミュニケーションは発信者自身の心情や人柄、人格までもが滲み込んだ振舞いによって届けられるのです。
◆対話とは「正・反・合」の共創作業である
コミュニケーションの中で、最も建設的で、しかしながら最も根気を要する形が「対話」です。対話を本記事なりに定義すれば、「考えていることを真摯に開き合い、互いが当初よりも高い次元の考えにたどりつこうとする語り合い」となるでしょうか。
ジャーナリストの立花隆氏は次のように書いています。「会話というのは、それ自体が一つのダイナミックな過程であり、対話者同士のインターアクションによって展開していくものである。弁証法(ディアレクティケー。もともと対話術の意味)的に会話をうまく展開させられれば、それはインターアクティブであることによってより高次元の認識に達することができる過程となる」(『二十歳のころ』より)。
ここで出てきた「弁証法的な発展」とは簡単には次のようなことです。一方に〈正〉という考えがあって、他方に〈反〉という考えがある。その双方が議論を重ねて、〈合〉という「第三の知」を新しく生みだすこと(図3)。

上司と部下との対話もまさに「正・反・合」の共創です。別に表現すれば、 「1+1=3」です。つまり、上司が「1」という自分の考えを差し出し、部下も「1」という考えを差し出す、あるいは上司が部下の「1」を引き出して傾聴する。そして新しい気づきである「3」を互いが得る。
対話とは単に双方が気休めで座談しているものではありません。高次元の結実を求める意志的な協働なのです。そしてこの協働によって生み出される「第三の知」こそ、組織文化の源となり、環境変化に対応していくための推進力になるのです。
◆互いの「べき・はず論」を超えて「共有目的」を置く
対話が重要な作業であるのは誰しも感じることなのですが、上司と部下において、なかなかこれができません。それはなぜでしょうか?―――
それは図2でみたとおり、上司には上司の文脈があって、上司はそこに乗ってコミュニケーションをしようとし、一方、部下には部下の文脈があって、部下はそこに乗ってコミュニケーションしようとするからです。たいてい両者の文脈にはズレが生じていて、そのズレが大きければ大きいほど対話はかみ合わなくなります。上司も部下もそれぞれが自分の「べき論・はず論」を前面に立てていて、歯車が共創回路に入らないのです。
次のページ「共有目的」(Common Purpose)
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
【部課長の対話力】
2010.08.23
2010.08.17
2010.08.10
2010.08.04
キャリア・ポートレート コンサルティング 代表
人財教育コンサルタント・概念工作家。 『プロフェッショナルシップ研修』(一個のプロとしての意識基盤をつくる教育プログラム)はじめ「コンセプチュアル思考研修」、管理職研修、キャリア開発研修などのジャンルで企業内研修を行なう。「働くこと・仕事」の本質をつかむ哲学的なアプローチを志向している。
 フォローして村山 昇の新着記事を受け取る
フォローして村山 昇の新着記事を受け取る