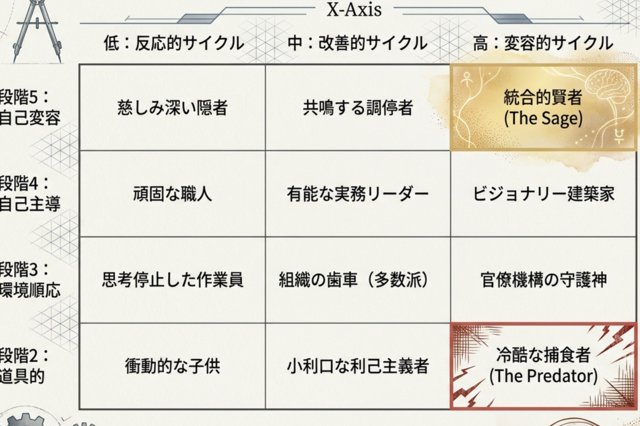生き残れる企業、淘汰される企業。その両社を分かつものは何なのか?
2010年1月18日日経MJのコラム「底流を読む」は、安売り悪者論は「負け犬の遠吠え」とバッサリで痛快だった。
ユニクロを例として出しているが、ユニクロの武器は低価格で高品質と指摘している。実際にはそれだけではない。ヒートテックやブラトップをヒットさせた「機能性」も見逃せない。さらにデザイナー、ジル・サンダー氏との契約で「デザイン性」まで追加した。ユニクロ傘下のサブブランドとして展開した「+J」には、季節毎の新商品購入のために発売日にはファンの数百人が行列を作る。
つまり、低価格戦争時代の生き残り策は、「低価格(だけ)で戦わないこと」なのだ。「ユニクロ=低価格」という図式を思い描く人は多いのだが、その思い込みは、あまりに古くて現状にあたわない。
「価値」と「価格」が正比例した関係を「バリューライン」という。「価格」は定量的絶対値だ。故に、工夫のしどころは「価値」を何と定義して市場に、顧客に訴えかけるかがキモになる。
他の例をみてみよう。
「長崎ちゃんぽん」の「リンガーハット」は昨年、具材の野菜を100%国産化し、さらに増量した。結果として商品価格上昇した。値上げをしたのである。結果は大成功。さっさと外食産業、特に「おひとり様向けカウンター外食」の低価格戦争から離脱している。
象徴的な商品がある。650円という同社メニューとしては前例がない高価格の「野菜たっぷりちゃんぽん」だ。450グラムという圧倒的に「たっぷり」な野菜の量で顧客の支持を獲得し、今では2割の客が注文するという。
さらに、二の矢も用意している。麺の小麦粉も国産化し「食の安心」を磐石にする。驚くべきことに、同時に麺の増量も無料化するという。
ちゃんぽんのサイドメニューであるライスとそのバリエーションと完全にカニバるため、その注文は激減するだろう。ライスを犠牲にしても、「割安感」を創出し、新規顧客のさらなる呼び込み、既存顧客の定着化が欠かせないとの判断に違いない。つまりは「選択と集中」である。
血で血を洗う激戦が繰り広げられ、まさに「レッドオーシャン」の牛丼業界を見てみよう。
関東地区だけに展開する「神戸らんぷ亭」。明らかに「フォロアー」のポジションである。だとすれば、消耗戦に参戦することは規模に劣り調達力が弱いため、圧倒的な不利が否めない。しかし、参戦しなければ顧客流出は止められない。同社は最低価格戦争に生き残りをかけて参戦した。大手と同じ最低レベルの「牛丼1杯280円」である。
そんな同社の生き残り一手は、「常識にとらわれない味」だった。
塩だれで味付けしたという「塩牛丼」。牛丼業界では従来も様々な味の工夫を各社がしてきたが、それは「あくまで、醤油ベースのタレの上でのトッピングのバリエーションに過ぎない」と神戸らんぷ亭は言い切る。従来商品は最低価格で提供し、注目を集める新商品はしっかり値下げ前の水準である380円を稼ぐ。客数と客単価のバランスを図る「マージンミックス戦略」である。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2015.07.10
2015.07.24
有限会社金森マーケティング事務所 取締役
コンサルタントと講師業の二足のわらじを履く立場を活かし、「現場で起きていること」を見抜き、それをわかりやすい「フレームワーク」で読み解いていきます。このサイトでは、顧客者視点のマーケティングを軸足に、世の中の様々な事象を切り取りるコラムを執筆していきます。
 フォローして金森 努の新着記事を受け取る
フォローして金森 努の新着記事を受け取る