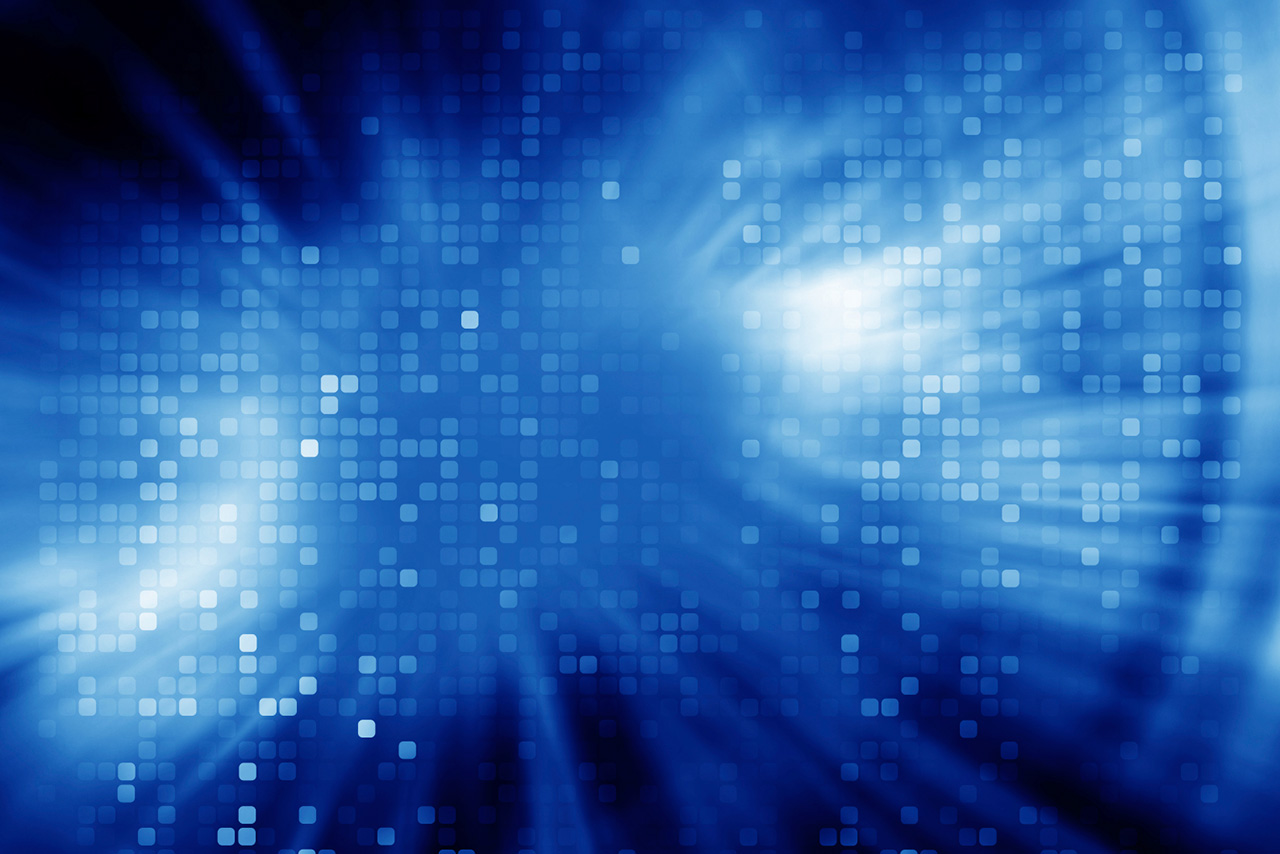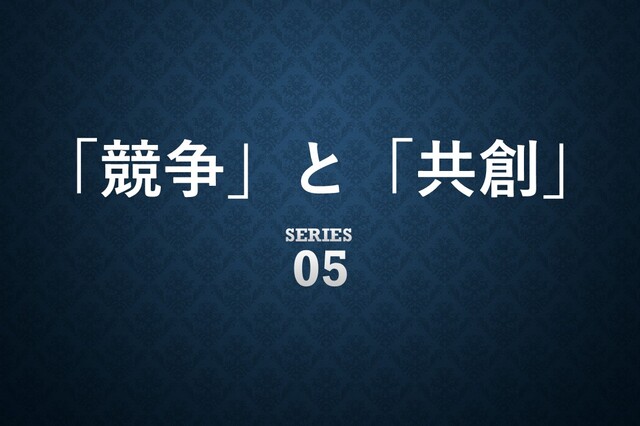2025年の調達購買のトレンド予測を4点ほどしてみました。
これはインターネットが出てきたころと全く同じです。ネットの黎明期は一部のマニアのツールだったのですが、Webの技術とWindows95の登場から一気にインターネットが普及しました。このころにはインターネットを活用して、情報収集をする人とそうでない人のデジタルデバイドが広がったと言われています。AIについても生成AIの技術とCopilotなど、使いやすい環境となったことで、個人の便利なツールとして活用が進んでいくでしょう。
2.官製値上げの継続(人件費高騰と下請法改正)
2023年11月29日に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が政府から公表され、2024年はその実行フォローが続く1年でした。私はこれを「官製値上げ」と呼んでいますが、この傾向は2025年も続くでしょう。人件費だけでなく、原材料費用やエネルギー費用の高騰、また円安による輸入物価の高騰など、官製だけでない購入費用の高騰は続きます。
今年の通常国会では約50年ぶりの下請法改正案の成立が目指されるとの報道がされています。改正内容については、公正取引委員会の公表資料や企業取引研究会の報告書を参考にすると、おおよそ把握できますが、従来難しいと言われていた「買いたたき」要件の行為類型を明確にする等が言われています。
ここでは親事業者が、一方的に下請代金を決定して、下請事業者の利益を不当に害する行為を規制対象とすることを検討しているようです。ポイントとしては、製造工程における温室効果ガスの排出量の削減を要請することなども問題視されるかもしれないということです。現在、様々な情報収集をサプライヤから定期的に実施している企業は多く、ごく一般的ですが、拡大解釈すると、そのような調査への協力依頼を一方的にすること自体が禁止される恐れもあります。
他には、支払手段として紙の手形による支払は認めない他、電子手形やファクタリングでの支払いの場合も支払期日までに下請代金の満額の現金と引き換えることができること、という内容も、バイヤー企業にとってインパクトが大きいかも知れません。
このように大きな意味での「官製値上げ」は今年も続くでしょう。
3.「川上と川下企業が中間企業を選ぶ」時代は続く
従来の、サプライヤマネジメントは直接取引のあるTier1のサプライヤを管理したり、関係性を構築することが中心でした。一方で、昨今の経営環境変化に伴い、チェーンの多層構造化が進むとともに、多くの分野で、川上側と川下側のプレイヤが相対的に力を持ち始めています。この傾向は今後、一層進んでいくでしょう。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
調達購買コンサルタント
調達購買改革コンサルタント。 自身も自動車会社、外資系金融機関の調達・購買を経験し、複数のコンサルティング会社を経由しており、購買実務経験のあるプロフェッショナルです。
 フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る
フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る