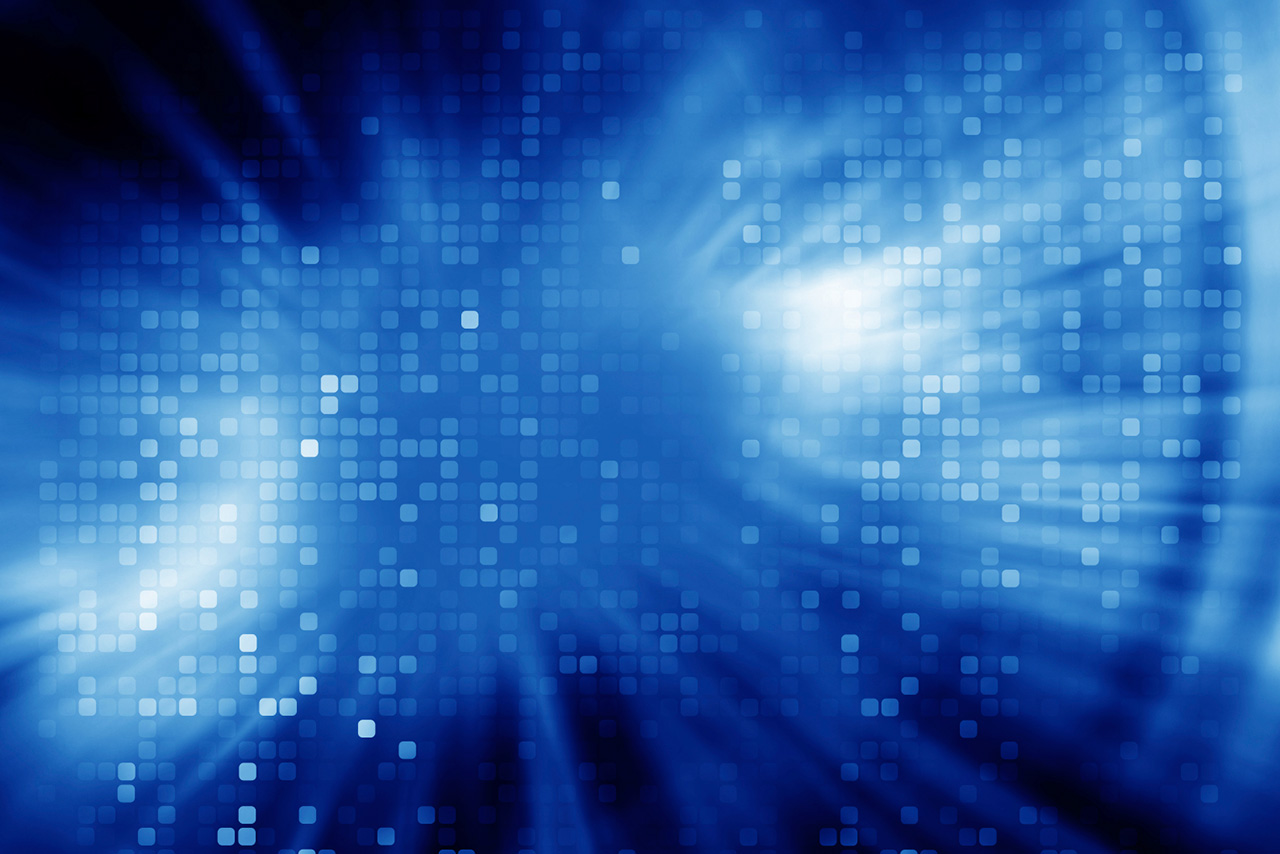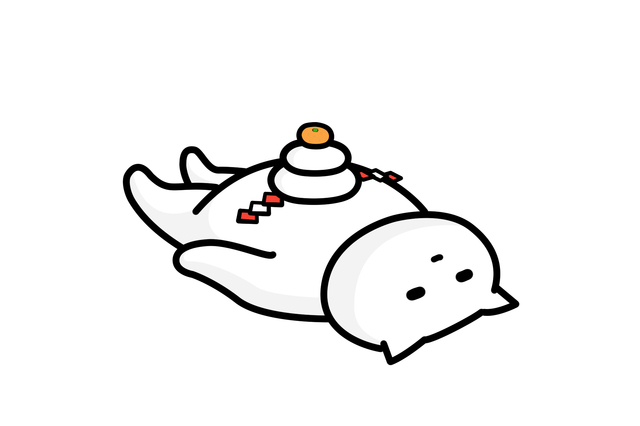ある編集者によると「ビジネス書の9割はゴーストライターが書いている」という。これまで彼らの原稿料や出版界の特殊な事情などに触れてきたが、今回は現役編集者からのタレコミをもとに、出版界の闇に迫った。 [吉田典史,Business Media 誠]
こういうところから、パクリの問題が起きるのではないだろうか。事実、ビジネス書の編集者と話すと「書いた本人が誰なのか分からない」とか「その文章の著作権の所在がハッキリしない」といったことが笑い話になる。中には、ほかの出版社と実際、パクリだとして争いになったこともあるという。
冒頭の女性編集者は、文芸誌の編集に関わることに誇りを持っている。「文芸誌では、こういった例は少数であってほしい」と話していた。会社の中では筋を通すと、生きにくいが、どうか乗り越えてほしいと私は思った。
著名な経営者の代わりに、ゴーストライターが書く
もう1つのケース。中堅出版社に勤務する30代の男性編集者は、ビジネス書を担当している。この編集部では、会社の経営者を著者に仕立てて、ゴーストライターを起用し、書くこととなった。ところが、当初からトラブルが起きた。
まず、経営者は始めの打ち合わせに20分ほど現れただけ。それ以降の取材(1回の取材は約2時間、これが5回に及ぶので計10時間)には来なかった。信じ難い話だが、編集者と会社とのやりとりをまとめた書類に目を通すと、信ぴょう性が高いと私は感じた。

取材は、経営者の名前で出す本でありながら、営業推進部や企画部のマネージャー、課長クラスが編集者やゴーストライターに話す。編集者いわく「めちゃくちゃな話し合いになった」という。そこに広報も加わり、資料などを提示する。それで「あとはよろしくお願いします」となる。ライターがそれを200 ページほどにまとめた。
ここで、さらに問題が起きる。今度は、関与していなかった経営者(表向きの著者)が原稿に目を通した。すると「創業のころの話がない」「上場した話がないと、いけない」と言い始める。それを受けて、編集者やゴーストライターが取材をする。しかし、経営者はそこに現れない。広報の社員が経営者に代わり、話す。それをライターが原稿に書き加えた。
さらに事態は、エスカレートする。今度は、経営者が新たにできた原稿を見て、「この本を世に出すのは当分、やめよう」と言い始めた。その理由は、「競合社から嫉妬(しっと)される可能性があるから」だという。ここまで来ると、悲しくなるほどのレベルなのだが、事実である。この会社に勤務するほかの社員からも、この話を聞いた。
私はこの編集者にも問題があるのではないか、と思った。彼に「なぜ、こういう経営者を著者にしようとしたのか」と聞いた。すると「社長や役員(編集長兼務)の指示」という。役員らは、経営者の知名度の高さやブランド力に関心があったようだ。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.07.05
2010.07.24
 フォローしてITmedia ビジネスオンラインの新着記事を受け取る
フォローしてITmedia ビジネスオンラインの新着記事を受け取る