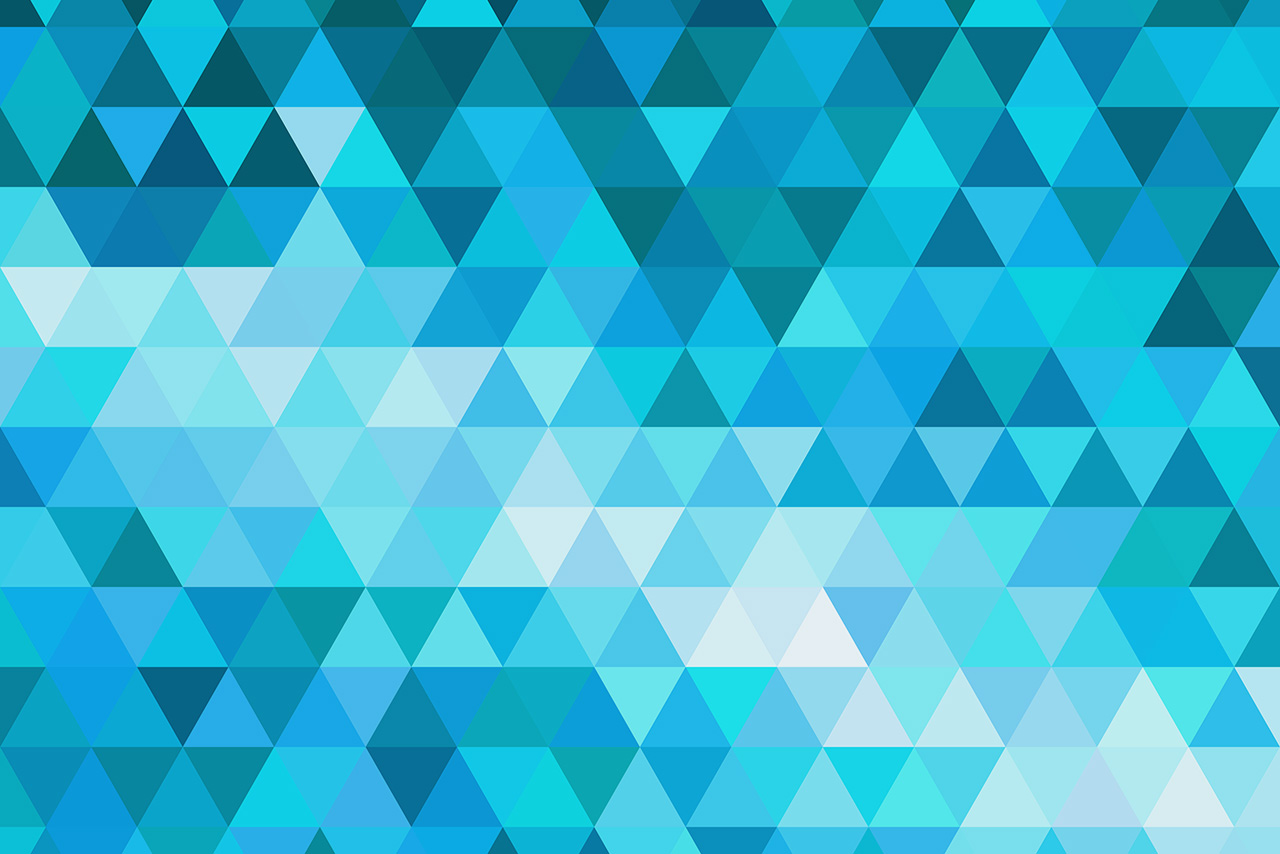企業を継続的に成長させる上で大切な人材採用。選考過程では筆記試験や面接などさまざまな試験が課されるが、それぞれにどのような意味があるのだろうか。複数の就活生や人事担当の方のお話を聞いた上で、アイティメディア総務人事部の浦野平也氏に補足いただいた。[森田徹,Business Media 誠]
基本的には、現場の責任者クラスが行う3次面接でほぼ選考は終了し、最終面接は建前上の最終確認になるケースが多いようである。「人事部としては、上の人に無駄な時間を使わせてしまうのは何よりの失態と考えて、最終面接は無難に受け答えしてくれればそれで十分、という場合がほとんどでしょう」(浦野氏)だそうである。
そういえば最終面接で「第1志望は我が社ですか?」と問われ、「いいえ、他社の○○です」と本音で答えたために「なぜか内定がとれない」と嘆いている知り合いがいたが、社会で必要とされるのはやはり本音と建前。社会人としての技量が問われる面接の場でも、それがきちんと使いこなせなければダメということだろうか。なかなか、難しい話である。
定性評価と協働性
ここまで話を聞いて感じたのは、戦略コンサルなど一部を除く大半の企業はとても曖昧な評価基準で定性評価を行って新卒を雇い、それで企業という1 つの独立した組織体系が回っているという事実の不可思議さである。一時期、成果主義の導入で日本企業が浮き足立った時期に、新卒採用の場で定量評価が流行ったという話もあまり聞かない。点数と偏差値という高度に完成された定量評価基準で選抜を受けてきた我々大学生にはやや違和感を覚える選定方法だが、それでいいのだろうか。
「ほとんどの企業において、組織がそれで回っているから、採用もそうなっているのだと思う」というのが浦野氏の返答だ。個々人の能力に基づく、結果のみを求める雇用における定量的評価は一見合理的で美しく完成されているように思える。しかし、たいていの仕事はそこまで高度にモジュール化されているわけでもなく、結果がすぐに出る訳でもない。それは筆者が社会人の真似事をしてありありと実感したことの1つである。また、モジュール化はおろかコモディティー化されていない仕事の結果の定量評価基準を作成すること自体が、実際には異常なほど手間がかかる。
そのような場においての定性評価で問われるものとは何だろうか? たまたま手に取った教育論の書籍『街場の教育論』(内田樹、ミシマ社)が1つの答えを提示していた。
次のページ「面接なんて、受ける側の能力次第でどうこうできるわけで...
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.06.18
2009.06.23
 フォローしてITmedia ビジネスオンラインの新着記事を受け取る
フォローしてITmedia ビジネスオンラインの新着記事を受け取る