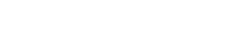世界の人口が年々増え続ける中、近い将来、家畜飼料の生産が追いつかなくなり、重要なタンパク源となる肉類が食べられなくなるかもしれない── そんな「タンパク質危機」への懸念が広まる近年、国内外で急成長しているのが、食品に関わる課題を先端技術で解決する「フードテック」と呼ばれる産業分野だ。 前回の《将来のタンパク質危機の挑むフードテック企業~1》では、肉類に替わる新たなタンパク源として「昆虫食」の研究開発を進める、日本のベンチャー・スタートアップ企業の取り組みを紹介した。 続く今回は、昆虫食とは異なるアプローチで将来のタンパク質危機に挑む、国内企業や研究機関の取り組みにフォーカス。さらに、地球から宇宙へと広がるフードテックビジネスの新たな展開と可能性について見ていくことにしよう。
さらに、新ジャンルのミートテックとして、ここ最近注目を集めているのが「人工培養肉」だ。これは動物から採取した細胞を特殊な培養液に浸し、筋細胞を増やして「肉に育てる」方法で、再生医療や創薬における細胞培養の技術が生かされている。培養肉は家畜生産より環境負荷が低く、衛生管理も容易なため実用化への期待が大きい。ただ、現在のところ培養肉の多くはミンチ状の段階で、ハンバーグやパテには向いても、ステーキ肉のような食感を出すのは難しいという。
日本の研究チームが実現した世界初の「培養ステーキ肉」
そうした中、日清食品ホールディングスと東京大学の研究チームは今年(2019年)3月、牛の筋肉細胞からサイコロステーキ状の組織をつくることに世界で初めて成功したと発表。研究チームは、牛の筋肉細胞を特殊な培地で育てて細長い筋繊維を作製し、層状に重ねて培養することで弾力のある立方体(1センチ×0.6センチ×0.7センチ)の筋肉組織を実現。今後はさらに大きな組織の作製に挑むという。
現時点ではコスト高が課題となるが、日清食品ホールディングスは「将来は巨大な市場が見込まれる。生産体制やコスト、安全性を検証し実用化を目指す」としている。東大研究チームの竹内昌治教授も「培養肉が大量生産され、スーパーで手軽に購入できるようになれば、将来の畜産を補う役割が期待できる」と話す。
月面で「地産地消」する宇宙食としての活用も
藻類や人工培養肉は、宇宙に滞在する際のタンパク源としても注目されている。
JAXA(宇宙航空研究開発機構)は今年3月、国内30の企業や大学などと連携して、将来の月面滞在で必要な食料生産システムの検討を開始すると発表。現在、人工培養肉のステーキや藻類のスープなど7品目のメニューが候補に挙がっており、藻類の活用事業を展開する「ユーグレナ(東京都港区)」や、人工培養肉の開発に取り組む「インテグリカルチャー(東京都新宿区)」などの企業が宇宙での食糧生産を担う。
人間が月に長期滞在するには、地球から持ち込む食料だけでなく、月面で手に入るもので「地産地消」する資源循環システムが必要となるため、滞在によって出るゴミや排泄物も活用することになる。インテグリカルチャーCEOの羽生雄毅氏は、「滞在施設の下水から得た窒素や炭素の成分と、月にある鉱物の栄養分や太陽光で藻類を育て、その藻類を使った培養液で人工培養肉を作れないか」と考えているという。これはまさに、食の完全リサイクル&リユースを実現する、究極のエコシステムといっていいだろう。
次のページ宇宙と地球で共通する食糧問題の解決に向けて……
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2015.07.17
2009.10.31